歴史系の小説読んだことありますか?
面白い作品と、面白くない作品の違いは余白にあります。歴史事実をひたすら淡々と並べているだけだと、眠たくなってしまいますよね。
感情を揺らすコンテンツを作りたい人は、少しお時間ください。
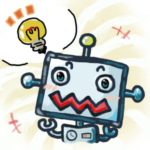
こんにちは!コンじゃぶろーです!
想像を超える力を持つ「見えない余白」。私たちの周りにある形や色、音など明確な形を持つものたちが放つ美しさや意味は、実はその間に存在する何もない空間、つまり余白によって大きく引き立てられています。この見えない余白が、いかにして私たちの想像力を刺激し、感情に深く響くのでしょうか。
余白とは、ただの空白ではありません。それは視覚的な休息の場であり、心に響く物語を紡ぎ出すための舞台です。デザインの世界では、この余白がもたらす効果を「負の空間」と呼び、その効果的な使い方が作品の質を大きく左右するとされています。しかし、このデザインの原理は、私たちの日常生活や感情にも深く関わっているのです。
本記事では、デザインにおける「想像の余白」の重要性を探りつつ、その心理的影響や、日常において私たちがどのようにこの余白を感じ取り、また創造していくことができるのかを考察します。余白を通じて、視覚と感情の間にどのようなリズムを生み出すことができるのか、その魅力を一緒に探っていきましょう。
余白は、目に見えない「何もない」ことで、「何か」を生み出す不思議な力を持っています。それは、私たちにとっての創造性の源であり、自己表現の場でもあります。余白の中には、限りない可能性が広がっており、私たちの想像力によって、その空白は色とりどりの物語で満たされていきます。
このように、「見えない余白」は私たちの心を豊かにし、日々の生活に新たな発見と驚きをもたらしてくれます。日常のささいな瞬間に、意識的に余白を設けることで、生活に柔軟性と豊かさをもたらすことができるのです。
本日の記事、重要なポイント
- 余白に感じる「自分」
- ちょっとした所に余白を作る
想像の余白を作る:創造力を刺激する空間の魔法

「想像の余白」という言葉を聞いたことがある人もいるかと思います。
余白って何だろうか?と考えると、見た人が自分で考える部分かなと思います。
見た目で言えば、何も描かれていない白い部分。感情的な部分で言えば、一部の感情が欠落した状態であったりするでしょうか。
わざと表現しなかったり、言葉を話さなかったりすると、そこに「余白」が生まれます。
余白がない状況というのは、見た人が考える余地が無い状態になります。対象の人が疲れている時とか、考えたくない時に余白があるとしんどくないか?と思ったりもしましたが、結構逆なんですよね。
これは感覚的な僕の考えですが、疲れている時って頭が情報でパンクしている時だと思います。こういう時は、ノートとかA4用紙に考えている事を書き出した方が楽だったりします。
脳の情報量を減らす快感というか、吐き出して楽になる感覚があります。
マインドフルネスとかもそういう所ある気がするんですけど、空白に情報を埋め込むと自分の脳の中の雑念が少しずつ減ってクリアになります。
考えない時間を作ったり、真っ白い用紙に余分な情報を捨てるような感覚で吐き出してやると、疲れが取れるんです。
疲れた時に、情報いっぱい詰め込まれた漫画を読んだりしたらしんどいですけど、セリフが一切ない漫画を読むと逆に癒されたりします。
「ひつじのショーン」とか、セリフがないので疲れた時にはおすすめですよ。
余白に感じる「自分」:内省と発見の旅へ


人は、余白を用意すると、そこに自分をうめていく習性があります。
登場する主人公に余白を用意することで、プレイヤーは自分が持っている情報で、その余白を埋めていきます。
自分の脳の情報を減らして、頭の中をスッキリしながら、少しずつ主人公の感情とリンクする。頭がスッキリするから、より主人公の感情に寄り添うように脳を働かせることができます。
こうやって、自分の分身にまで成長した主人公が冒険することで、ハラハラしたりドキドキしたりできるわけです。
有名な画家が描いた絵っていうのは、見た人を遠い場所へ瞬時に連れていく強さがあります。
ゲームや小説も同様で、電車の中でも仕事の合間でも、瞬時にファンタジーへ旅ができるので、脳に刺激を与えることができるんです。
余白が無いものは、感情移入しづらい:親近感を生むデザインの秘訣


余白がないものは感情移入しづらいなぁと思ったことないでしょうか?
歴史系の小説には、情報を並べただけの年表的なものがあります。そういうものは、全て書いてくれているので親切だったりするんですけど、面白くないんですよね。
ゲームの提案書だってそうです。
情報を全て詰め込めば、伝わるわけではありません。
情報は必要最低限に抑える。そうして生み出した「余白」に、見た人の感情で保管してもらう。
そうすれば、読んでいる人が自然と「仲間」になってくれたりします。
うまい人の作品は、まず「余白」を使って、読み手の感情を揺さぶり、その後、必要最低限の情報だけ渡すようにしています。
情報を伝えるのが目的ではなくて、感情を揺さぶるというのが目的だからですね。
感情の余白がない作品を読むことで、この辺りのことがよくわかるかもしれません。歴史年表みたいな小説を読んでみましょう。いや、むしろ歴史年表を探して読んでみるとすごくわかると思います。
余白が無いって「しんどいなぁ」そう思えます。
意外と多い余白の設定:見過ごされがちなデザインの力
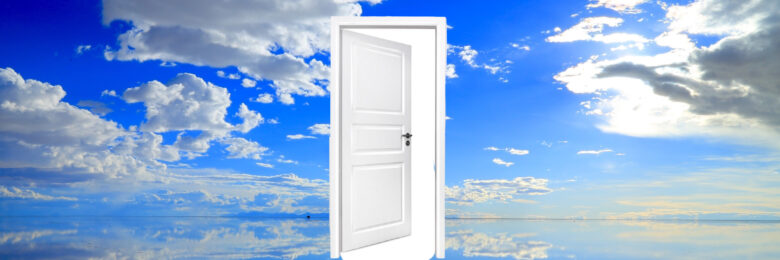
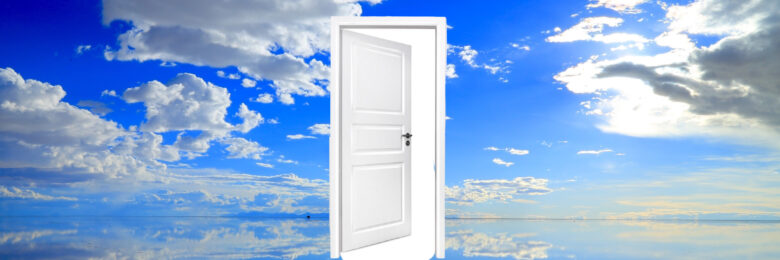
世の中の作品には、意外と多くの余白が存在しています。
キャラクターで言えば、「感情」を空白にする表現です。「教師」や「看護師」といった職業は、個性や感情が職業に消されるので、感情移入しやすい余白になります。
また、ゲームであれば、完全に喋らない主人公というのも存在します。
「言葉」を余白にすることで、プレイしている人が自分の「言葉」を埋めていくことができます。代表的なものに、ドラゴンクエストがあります。確か、最後の最後だけセリフを言ったりします。それまで一切喋らないことで、個性が生まれています。
作り手側が主人公に喋らせる部分を極限まで削ることで、壮大なストーリーを作り上げています。
鬼滅の刃に出てくる根津子も、言葉を話さないキャラクターですね。言葉を余白にすることで、作品へ引き込むことができます。
漫画家は特に、さまざまな余白を作るスペシャリストです。
それぞれの巨匠が、どういった「余白」を用意しているのか?そういう視点で読み進めると、とても面白い気づきがあります。
- 作品に触れた人は、余白に感情移入していく
- 余白がないと、感情移入しづらい
- 余白に意識を向けると、作品の印象が変わる
ちょっとした所に、余白を作る:日常に潜む創造性を引き出す


余白は、作品にリズムを生むことができると考えています。
漫画を流し見してみるとわかるんですけど、どんな漫画を読んでも漫画の個性を感じることができます。リズムオンリーに着眼して、漫画を読んでみるのも面白いですよ。
巨匠と呼ばれる人は、リズムを作る技術がすごいと感じます。
漫画やアニメ、小説、映画、ゲーム、さまざまな媒体でさまざまな「余白」が作られています。
小説の世界には、文字の字間を調節する専門家「ブックデザイナー(装丁家)」がいるくらいなので、「余白」をデザインすれば、作品の評価が大きく変わることが知られています。
作品に余白を作る方法は色々あると思いますが、大きく分けて「視覚的な余白」と「感情的な余白」かなと思います。
視覚的な余白:目に見える「静けさ」の価値


視覚的な効果が人に与える印象は、7割と言われています。それくらい視覚的な情報が影響がある部分なので、ここに「余白」を入れるのはとても良い方法だと思います。
見た目にシンプルな服装をしている場合は、感情移入しやすいですし、描き込みが多い服装の場合は、感情移入できる部分が減り「カリスマ性」が生まれると思います。
感情移入してほしい部分があれば、空白の多いデザイン。逆に感情移入させたくない部分には「余白」がない部分にする。
余白を強調する為に、周りを密にするといったテクニックもあったりします。目線の移動も、「余白」でできたりします。
視覚表現を使った「余白」のテクニックはキリがないですね。
感情的な余白:心に響く「無音」の重要性


視覚的なものを除いて、次に重要なのは「感情」に訴えかける「余白」です。
視覚的な表現に比べて、気づかれづらい「余白」なので、気づかない人も多い部分だと思います。けれども意外と重要な要素を占めているような気がします。
一切怒らないキャラクターを用意した場合、「どうしてそんな性格になったのか?」という経緯に興味が湧きます。あるいは、自分の怒りの感情で補完することで、自分の分身のような感覚が湧き上がることもあるでしょう。
作品の中の余白に自分の居場所を見つけることができれば、まるでそこに住んでいるような錯覚さえ感じたりします。
目には見えない感情の余白は、作品に深みを与えていきます。
- 余白がリズムを生む
- 視覚的な印象が7割、視覚の余白がリズムを作る
- 感情的な余白が、深みをもたらす
まとめ 想像の余白が、感情にリズムを生む:デザインにおける心理的影響


昔から、「余白」って何の為に用意するんだろうと考えていました。
いまほど、しっかりと答えは出てなかったので、漠然と感情移入する為に必要なものだと思い、ゲーム開発していた時は意識的に「余白」を盛り込んでいました。
昔から、歴史小説を読むのが好きで、色々と読んでいましたが、余白がない歴史年表見たいな小説は、本当に面白くないんです。
その違いは、やっぱり全部説明しすぎない「余白」にあるかな?とか考えながら開発してきました。
今は、「余白はリズムを生むもの」という答えに落ち着いているわけですが、コツコツ続けていれば、より深い答えにたどり着くかもしれません。
まるで音色が聞こえてくるような、そんなものに出会うと感激すら覚えます。
ゲームで言えば、「ゼルダの伝説」です。主人公は一切喋らないです。シリーズで言えば、「夢をみる島」や「ムジュラの仮面」が好きですが、シリーズを通して「余白」がとても美しいです。
小説で言えば、吉川英治の「三国志」です。「音」が無いはずなのに、まるで歌でも聴いているかのような気分になります。
「余白」をうまく作って、人を惹きつけるゲームを作りたいなぁと思います。
以上、さしあたり、今思う事でした。
ここまで読んでいただけてありがとうございます。
皆様の良い人生の一助になれば。
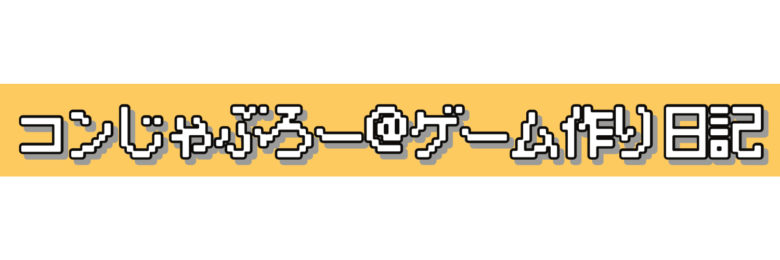





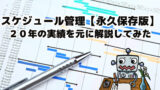

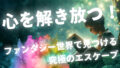
コメント