オリジナルキャラクターを考えたけれど、魅力的にならない…。
そんなクリエイターの方はこちらの記事をどうぞ!
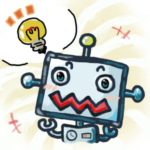
こんにちは!コンじゃぶろーです!
この記事を手にしたあなたは、おそらく物語の心臓部とも言える「キャラクター創作」の秘密を解き明かしたいと考えていることでしょう。物語にとってキャラクターは、読者や視聴者の心に残る重要な要素です。キャラクターが魅力的であればあるほど、物語は色鮮やかに、そして深みを増していきます。
創作活動において、キャラクターに魂を吹き込むことは、単に外見や設定を考えること以上の意味を持ちます。それは、彼らを「生きている」と感じさせ、読者が共感し、時には自らを投影できる存在にすることです。しかし、このプロセスは決して容易ではありません。多くの作家がこの難題に直面し、どのようにしてキャラクターを紙の上で生き生きとさせるか、日々試行錯誤を続けています。
この記事では、キャラクター創作の根幹をなす、いくつかの重要なポイントを掘り下げていきます。存在意義の探求から、キャラクターの弱点やトラウマに至るまで、感情を揺さぶるキャラクターを創り出すための具体的な方法を紐解いていきましょう。リアルな「クセ」の取り入れ方、生年月日と姓名判断を用いた性格設定、そして、キャラクターが直面する最大の挑戦や問題の設定によって、彼らの内面を豊かにし、読者が感情移入しやすいキャラクターを創り出すための秘訣をお伝えします。
物語の中でキャラクターたちは、読者の心を動かし、感動を呼ぶ力を持っています。それぞれのキャラクターが持つ独自の背景や性格、彼らが乗り越えるべき試練や成長の旅は、読者自身の体験や感情と重なり合い、忘れがたい印象を残すのです。
ここから始まる「キャラクター創作の旅」にあなたも一歩を踏み出しましょう。私たちは、あなたが創り出すキャラクターたちが、読者の心に深く刻まれる存在となることを願っています。さあ、魅力的なキャラクター創作の極意を、この記事を通じて一緒に探求していきましょう。
本日の記事、重要なポイント
- キャラクターを生み出す時の基本
- キャラクターに魂を込める方法
キャラクターに魂を込める創作の旅
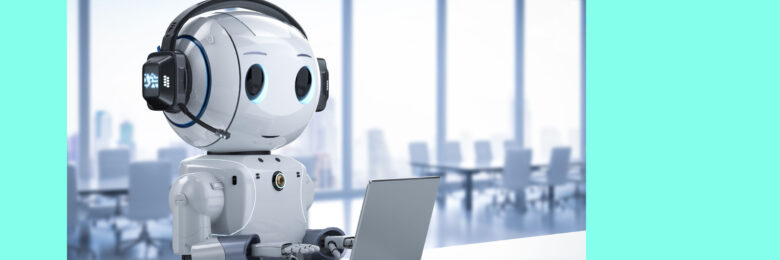
この記事を読んでいるという事は、ゲームや漫画、小説等、キャラクターに関する仕事をした事がある人かもしれません。
ゆるキャラを作る自治体とかもあるくらいなので、どんな人がキャラクターを作るのかわからない時代です。
架空のキャラクターを生み出して、SNSで活動するというのも、今風で、アリかもしれませんね。
今日は、キャラクターの生み出し方に関しての解説です。
ぶっちゃけた話、キャラクターは誰にでも作ることが可能です。
しかし、魂を込めれる人は、それほど多くありません。今日の記事を読めば、誰でも魂を込めることができるようになると思います。
キャラクター創造の基本

まず、架空のキャラクターを生み出すには、キャラクターのプロフィールを考える必要があります。
「どんなキャラクターを生み出すか?」を考えるのが、一番難しい所だったりします。
目的によって、キャラクターの設定は大きく変わるからです。
例えば、「10代に人気のバーチャルアイドル」とか、「老人ホームで、おじいちゃんやおばあちゃんの相談に乗る優しい女の子」「40代の社会人を怖がらせるサイコパス」と、いった感じで「目的」や「ターゲット」を絞らなくてはいけません。
存在意義の探求

このキャラクターは、誰の為に存在するのか?
これが、クリエイターがキャラクターを生み出す時に最初に考えなければいけないことです。
ここが決まっていないと、この先を読んでもほとんと意味がありません。
これ以降の項目を決める時に、いちいちここで決めた「目的」に立ち戻ってください。
このキャラは、誰の為のキャラなのか?何をして、ターゲットに何を与えるのか?
ターゲットは、このキャラに何をして欲しいのか?
自己肯定感ならぬ、キャラ肯定感です。
どんなキャラクターでも生み出すことができるからこそ、その目的を明確にしなければいけません。
ゲームであれば、ストーリーの上で、どういう役割をしているのか?を明確にしなければ、読み手に伝わらないので、「役割」にも意識を向けなければいけませんが、そこを広げると収集がつかないので、ひとまず「主人公」を決めると言う限定条件で話を進めます。
設定の重要性とその基礎

物語の「主人公」は、読み手が感情移入する存在です。
なので、何の為?という問いに対しては、「○○歳あたりの読み手が、感情移入できる。そして○○という感情を満たしてくれる」「成長を追体験できる」といったことで問題ないと思います。
ここまでできれば、ほぼ、キャラクターデザインはできたも同然なんです。
キャラクターの目的をもとに、基本的な設定を考えましょう。ここは、穴埋め問題のように淡々とと決めればイイです。次の項目を考えてください。
キャラクターの目的・役割を基に考えることができれば100点満点です。
- キャラクターの名前:苗字と名前療法考えてください。
- 年齢
- 性別
- 性格
- 喋り方のくせ
- 価値観
- 容姿の特徴(髪型、髪の色、身長、体重、3サイズ)
- 一番大切にしていること:座右の名 等
- 職業、学歴
- イメージ写真:俳優やモデルなど、親和性の高い人の写真を集めます。
- イメージソング:キャラクターイメージに合う音楽を選定します。キャラクターの絵を描く時の助けになります。
キャラクターの目的と合っているかどうか、説明できれば素晴らしいですが、最悪説明できなくてもOKだと思います。大事なのは、自分が納得しているかどうかです。
経験を積めば、全て説明できるようになりますが、経験がなければ、理由を説明できないと思うので、「自分に嘘をつかない」ことが守れていれば最低限クリアだと思います。
僕も、最初の頃は、そんな感じでした。それでも、魂がこもっていれば必ず読み手には伝わりました。
避けるべき共通の落とし穴


僕が、キャラクターを、生み出す時に、絶対にやらないと決めていることがありました。
それは、「実際の名前」を使わないということです。
もし、自分が作った作品に、同姓同名の人がいたら、その人はどう思うでしょうか?たとえ、良いキャラクターで合っても、あまり良い気持ちではないと思います。
なので、僕は、必ずこの世に存在しない名前(実在しそうにない名前)をつけました。
「キラキラネーム」というのが流行った時期は、正直困りました。ゲームで考えるキャラクターの名前よりも、ぶっ飛んだ名前の人が急激に増えたからです。
キャラクターに愛情があるからこそ、名前被りを避ける。1人でも不快に思う人が現れないようにする配慮は、必要だと思っています。
- キャラクターの存在意義を考える。
- キャラクターの存在意義を考えながら、キャラクターの基本設定を考える。
- 実在する(しそうな)名前をつけない。
キャラクターに魂を吹き込む設定


キャラクターの目的を決めて、基本的な設定を考えれば、もうすでにキャラクターとして誕生しています。グラフィッカーへキャラクターデザインの依頼をすれば、描いてもらえるレベルだと思います。
あとは、シナリオを作り込みながら、キャラクターに磨きをかけていけば、そこそこ良いキャラクターに育ってくれます。
ただ、足りないものがあります。僕は、ここで「生々しさ」を追加するようにしています。
これがあるのとないのとでは、仕上がりに大きな差が生まれるように思うからです。
リアルな「クセ」の取り入れ方


自分の周りにいる人、あるいはテレビやYoutubeで見かける人。
キャラクターの存在目的と合致している人をチョイスして、その人の「クセ」を1つキャラクターの設定に追加してください。
- マイ醤油を持ち歩いている
- スマホ画面がバキバキ
- とにかくよくモノを落とす(無くす)
- 普段は優しいけれど、車の運転中に舌打ちする
- 酒が入ると豹変する
- 嘘をついた時に、左の眉が上がる
これらの情報は、ゲームの中で登場しない部分(裏設定)です。
シナリオや絵を作る際に、キャラクターをブレさせない為のおまじないです。
モデルとなる実際の人物の特徴を1つ追加することで、突発的なイベントが起きた時の反応がイメージしやすくなります。
これまでに設定した基本的な設定も全てその為にあるわけですが、実際にいる人をイメージできるので、キャラクターの存在感が出て生々しくなります。
生年月日と姓名判断による性格設定
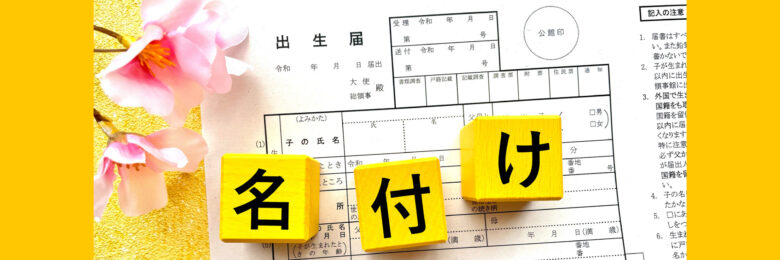
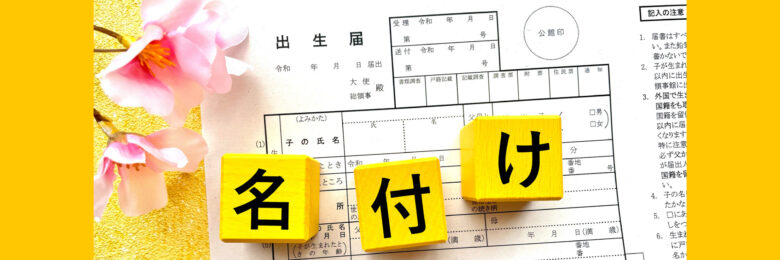
生年月日と名前があれば、占いをすることが可能です。
これまでに決めた設定で占いをしてみてください。「生年月日 占い 姓名判断」等で検索すると、そういったサイトが山程出てきます。
作ったキャラクターを占うと、その設定がもつ運命を可視化することができます。
ここに来るまでの設定で魂がこもっていれば、設定した性格と、占い結果が一致したりします。
もし、一致しない場合は、生年月日と名前を少しずらして試してみてください。自分では思いつかないような設定が追加されて、キャラクターの「魂」が濃くなることを感じれると思います。
弱点やトラウマを設定する意義


キャラクター最後の仕上げをします。
キャラクターの弱点を決めます。トラウマや、人生で1番悩んでいることを考えてください。
この作業は、キャラクターの基本設定ができるまでできない作業です。
キャラクターの基本設定は、生まれた直後の運命によるものですが、ここからは成長の過程、あるいは未来のことだからです。
自分で設計したキャラクターをイメージしてください。
このキャラクターは、いつどんな悩みを抱えるでしょうか?
主人公には大きな悩みが必要です。読み手が受ける最初の印象と、読み終わった時に感じている感情の「差」が、その作品の価値だからです。
「○○な主人公が、○○という経験を経て、○○へと成長した。」そういう差があるからこそ、読み手が成長を感じることができて、読んで楽しかったと感じるわけです。
スラムダンクで言うと「不良だった少年」が「バスケットボール」を通して更生し、「全国大会に挑む」みたいな感じでしょうか。
- キャラクターには、生々しさを盛り込む
- 生年月日占いや、姓名判断で答え合わせする
- キャラクターの弱点を考える
まとめ キャラクターに愛情を込めて


今日は、主人公に関してのキャラクター設計に関してまとめてみました。
実際には、主人公に立ち向かう強敵(ライバル)であったり、精神的支柱であったり、変化をもたらせる存在だったり。主人公を惑わせる役割もあるかもしれません。さまざまな役割のキャラクターが登場してきて話を盛り上げるわけです。
もし、興味がある方は、一度、好きな漫画やアニメ、映画のキャラクターを、今日の基本設定に基づいて書き出して行ってみてください。
僕も、最初はそんな事ばかりしていました。
ストーリーにとって、どんな「役割」を持っているのか?と言う視点ができると、作品を見る目が変わってくるかもしれません。
新しい目を持てば、誰でもキャラクターは生み出せる。僕はそう思います。
以上、さしあたり、今思う事でした。
ここまで読んでいただけてありがとうございます。
皆様の良い人生の一助になれば。
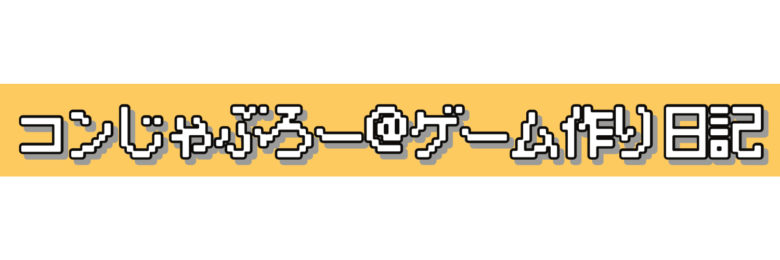









コメント