子供が、動画ばかり見たり、ゲームばかりしている…。
熱中するのは良いことだけど、もっと外で遊んでほしい…。
親というのは、悩ましい役割ですよね。
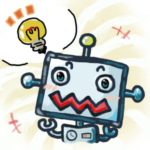
こんにちは!コンじゃぶろーです!
現代社会において、子供たちが目にする世界は、かつてないほど多様で複雑です。一方で、親としては、子供に見せたいもの、伝えたい価値観、そして未来へ向けた教育のあり方について、深い思いや願いがあります。この複雑なダイナミクスの中で、我々はどのようにして子供たちの成長をサポートし、正しい方向へ導くことができるのでしょうか?
子供と親、未来を見据えた教育のあり方を考えてみましょう。
現代の子供たちは、インターネット、ソーシャルメディア、そして多種多様なデジタルメディアに囲まれ、無限の情報にアクセスできる環境にいます。子供が「見たいもの」とは、一瞬一瞬で変わる興味の対象かもしれません。その一方で、親が「見せたいもの」とは、時に古典的であったり、教育的価値が高い内容であったりします。これらはしばしば、子供たちの求める「面白さ」とは一線を画すものです。
このギャップをどう埋めるかは、今日の親にとって大きな課題です。しかし、これは単なる好みの違いを超えた、より深い問題へと繋がります。それは、子供たちが将来生きる世界への準備です。今日見せるもの、教えるものが、彼らが大人になる頃の未来にどのように影響を及ぼすのか、その見通しは誰にも明確ではありません。
この記事では、子供と親の間に存在する「見たい」と「見せたい」のギャップに焦点を当て、そのギャップをどのように橋渡しするか、そして最終的には未来を見据えた教育のあり方をどう考えれば良いのかについて探求します。教育の目的、子供たちの興味をどう引きつけるか、そして親として何ができるのか。これらのテーマを通じて、読者の皆様と共に、子供たちの豊かな未来を築くためのヒントを見つけ出したいと思います。
子供たちが見たいものと親が見せたいものの間には、一見、溝があるように見えますが、この記事を通じて、それが実は新しい可能性への架け橋になり得ることを、一緒に考えていきましょう。
本日の記事、重要なポイント
- 親が見せたいものは、経験にもとづく
- 子供は面白い事にしか興味を持たない
子供が見たいモノ、親が見せたいモノ

子供はただ、見たいものを見ているだけだと思います。
親は、動画を見て育った訳ではないので、動画ばかり見て育った子供がどうなるか分からないという不安があるのではないでしょうか?
こういう場合、自分の経験を元に答えを導き出す必要があるので、好きなことばかりして、勉強や仕事をおろそかにした場合、苦しい未来が待っている。そう思ってしまうのも無理はないと思います。
特に、僕のように今40歳付近の世代は、就職氷河期でしたから、就職できず「ニート」状態になっている人は周りに多かったです。
「遊んでばかり」だと危ないと感じるのも無理はありません。ただ、なんでもかんでも「無し」とするのはちょっと乱暴で、思考停止は良くないので、しっかり見極める必要があります。
今日は、そのあたりの事に関して、就職氷河期世代で子育て中の僕が思うことをまとめたいと思います。
親が見せたいモノ

親が子供に見せたいものってなんでしょうか?
改めて考えてみると、あまり明確な答えはなかったので戸惑ってしましました。親になれば、誰もが考えなければいけない部分です。イメージできないことは、実現できないので、何も思い浮かばなかった場合、何も形になりません。
だから、親は子供に何を見せたいかを、しっかり考えてあげる必要があります。
経験から学ぶ:親が伝えたい価値観

それで、僕が自分の経験上必要だと思ったのは、「知識のアンテナを立てる」と「情報の調べ方」、そして「失敗から立ち上がる経験」です。
知識のアンテナと、情報の調べ方は、Youtubeで十分です。失敗から立ち上がる経験は、ゲームで可能だと思いました。ゲームは、「リトライ」ができる点からも、トライアンドエラーの繰り返しで構成されています。
でも、Youtubeやゲームばかりをさせるのは流石に心配という人もいると思います。
自分の若い頃の経験で、テレビやゲームで遊んでいる人を横目に勉強を頑張っていた人にとっては恐怖なのではないでしょうか?
しかし、そこに落とし穴が潜んでいるので注意が必要です。
時代を超えて:昔と今の子供たちの違い


今の大人が子供の頃、お金の格差も大きかったですが、情報の格差も相当大きなものでした。下手をすれば、そちらの方が大きいかもしれません。
それが、インターネットの登場によって急速に格差がなくなってきました。Youtubeには無料で有益な情報が溢れています。
そんな世界に住む今の子供と違う環境で育った大人達が、自分の感性だけで判断してしまっていいんでしょうか?僕は良く無い気がしています。
しかし、古い価値観がダメとしてしまうのも、なんだか勿体無いです。
無料で情報を入手できる点では、今も昔も「図書館」というものがありました。
江戸時代から続くエンタメもありますし、孫子の兵法書なんて今でも役に立ちます。時代が目まぐるしく変化しても、変わらず重要なこともあるはずです。
時代に関係なく、通用するものも必ずあるので、物事の原理原則を意識する必要があると思います。
- 自分が育った頃の時代と、今は違う
- 無料で、すぐに手に入るようになった情報
- 時代に関係なく古くから通用する原理原則を知る
子供はおもしろい事にしか興味を持たない


子供は、面白くない事はしません。
ちょっとでもつまらないと感じたら、やめてしまいます。「飽きる」というやつです。
子供は、遊びながら学ぶという点で、本能的に生きることに必要なことを学んでいます。僕が子供の頃は、みんなテレビを見ていたので、人気番組を見ていないと話についていけないというのがありました。
みんな同じゲームをしていたので、攻略情報を共有してコミュニケーションできないと「村八分状態」になりかねませんでした。
だから、みんな必死にテレビを見ましたし、ゲームもしました。
そうやって、生きる為に必要なことを学んでいるんです。そして、その嗅覚が鋭い人が生き残る。そういう方法で生き残ってきたのが今の人類です。この嗅覚を侮ってはいけません。
未来の予測:子供が大人になる世界


今の子供達が大人になる頃の未来は、どうなっているでしょうか?
それは正直誰にもわかりません。何を与えれば正解なのかなんてわかりません。親は、自分の経験から子供に与えるものを決めてしまいがちですが、「本当に正しいのか?」という意識を持たなければいけないと思います。
2000年前から変わらない原理原則としての「子育て」に意識を向けなければいけません。ただ、日本では、昔からそれができていた種族でもあるように思います。
ある程度、若い人に「やってみなはれ」という文化であったり、「可愛い子には旅させろ」そういうマインドです。
いつまでも、指示ばかりしていると、自分で判断できなくなるので、早いうちに任せて、失敗させる。あるいは、「失敗から立ち上がれるようにする」といった方法で伝えてきたように思います。
戦争や災害で多くの大人達がいなくなっても、立ち上がってきた日本には、そういう強さがあります。
リスクへの考え方:大人と子供の違い


子供と大人の違いってなんでしょうか?
それは、大人は「リスク」ばかり考えることではないでしょうか?
100%面白い映画しか見ない。100%満足できる店にしか行かない。サービスを利用した時は、減点方式で不満を蓄積し、いつしか悪い部分しか見なくなっている。
そうやって、新しいものに手を出す「リスク」を意識しすぎて、変化することに臆病になっているかもしれません。
お金と命の時間を捧げる訳ですから、それも仕方ないことかもしれませんが、「リスク」と「リターン」のさじ加減を判断するには、誰よりもそれを体験する必要があります。
だからこそ、可愛い子には、積極的に旅をさせるべきだと思います。大人も、子供と同じことに挑戦して、判断力を鍛えていかなければいけません。
- 今の子供と、昔の子供が生きている世界は違う。
- 可愛い子には旅させろ
- 大人も、挑戦する時代
まとめ:親は何をすべきかを考える


子供が見たいものと、親が見せたいものには、今後もジレンマは生まれ続けていくことでしょう。
時代の変化が強いほど、そのジレンマを大きなものになります。そういった中で、大人の古い経験で縛るのは良くないかも?そういう意識も時には必要なのではないかというのが、今日の記事の伝えたいことでした。
親がしいたレールに子供を乗せる。そういう方針もありだと思います。なぜなら、それも1つの答えだからです。
ゲームや動画を、子供が求めるなら見せるべきというのが、僕の持論ですが、安易にゲームや動画に子育てさせるのは「育児放棄」と変わらない状態になる場合もあります。
どちらも一長一短。
自分の子供の将来の為に、親が何をすべきかを考える。そして、そばで寄り添い一緒に歩くことが大切だと思います。
以上、さしあたり、今思う事でした。
ここまで読んでいただけてありがとうございます。
皆様の良い人生の一助になれば。
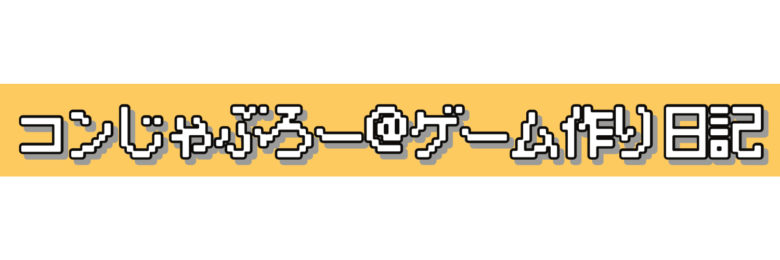










コメント