優秀なエンジニアが集まらない…。
優秀な人ほど辞めてしまう…。
人材リソース集めに苦労しているチームは多いですよね。そんな方はこの記事をどうぞ。
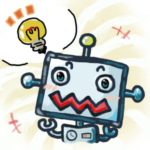
こんにちは!コンじゃぶろーです!
ゲーム開発の世界は、常に変化しています。新しい技術の登場、プレイヤーの趣味思考の変化、そして市場の動向等、さまざまな要素によって移り変わっています。今回取り上げるテーマである「シェアリングエコノミー」も、ゲーム開発の世界に変化をもたらすものの1つです。
シェアリングエコノミーとは、所有ではなく共有を通じて価値を生み出す経済システムを指します。AirbnbやUberといった企業は、このアイデアを利用して巨大なビジネスを築き上げました。そして今、この革新的な思考がゲーム開発にも応用されています。この新しいアプローチにより、開発リソース、ツール、さらにはアイデアまでもが、これまでにない方法で共有され、多様な才能が一つのプロジェクトに集結することが可能になりました。
この記事では、シェアリングエコノミーがゲーム業界にもたらす具体的なメリットと挑戦についても詳しく解説します。例えば、未経験者でもゲーム開発に参加しやすくなることや、開発プロセスの透明性が高まることなど、多くのポジティブな変化が期待されます。
しかし、共有されたリソースの管理、知的財産権の扱い、品質保持のための新たな基準の設定など、解決すべき問題は少なくありません。
本日の記事、重要なポイント
- シェアリングエコノミーとは?
- シェアリングエコノミーで、ゲームを作る。
シェアリングエコノミーの定義とゲーム開発への応用


スキルは、シェアする時代になっています。フリーランスや契約社員、など、短期的に協力するスタッフなくしてゲーム開発は難しい時代になっています。
開発するゲームのボリュームが大きくなっているというのも理由でしょうが、もう1つ多いきな課題があります。それは、社員として会社に所属すると「生産性」が低くなるケースがあるからです。
最初に終身雇用を推進したアメリカは、割と早い段階で破綻してしまい、終身雇用を捨てました。一方、日本は割と長く続ける事ができました。しかし、そこが落とし穴でした。
終身雇用を推進した結果、日本企業の生産性が低くなってしまったのです。
日米やヨーロッパの先進国38カ国が加盟するOECD(経済協力開発機構)。このOECDの中で日本は生産性が23位という結果になりました。
終身雇用の良い面は、社員が安心して仕事に専念できるという点です。
しかし、デメリットは、雇用主はかなりのコストを支払わなければいけないという点と、社員の向上心低下による生産性の低下です。
雇う側と雇われる側で、責任感がフェアではないので、最初の入社試験までを頑張る人が増えてしまう結果になりました。
日本人が、社会に出てから勉強に使う時間は、6分だそうです。
もちろん、通信制の大学や専門技術のスクールに通いながら、1日3時間から4時間勉強している人もいるので(ゲーム業界では、時間外に好きでプログラミングしたり絵を描いたりする人が割といます。)、それを加味すると「大半の日本人は、6分も勉強していない」が正解かもしれません。
シェアリングエコノミーの基本概念


シェアリングエコノミーとは、空いている資産をシェアする仕組みの事です。
空いている資産がある人は、貸主としてお金を受け取ります。そして、必要としている借主は、使用したい時にお金を支払って利用する。そうすれば、それを維持する費用を抑える事ができます。
車や家等の物理的な資産から、自分の技術までシェアする考え方です。
↓シェアリングエコノミーに関しては、総務省の情報通信白書に詳細な記載があります。

人を雇うと、社会保険や税金等の費用がかかってきてしまう為、かなりコストが高くなりますが、スキルをシェアするだけであれば、少ない費用で仕事を割り振る事ができます。
これまで、空いている資産があれば、人知れず放置されていました。
ささやかな放置が全国規模で発生すると、大きなロスとなり、国全体の生産性低下につながってしまいます。
代表的なシェアリングエコノミー企業とその影響
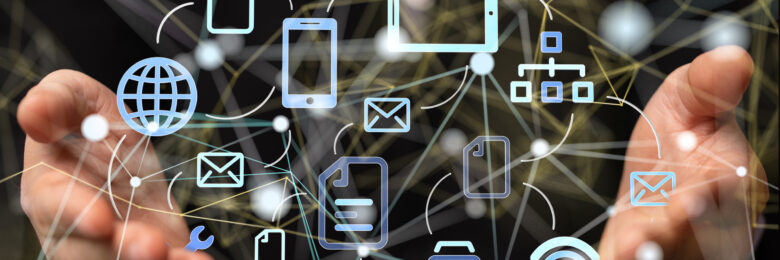
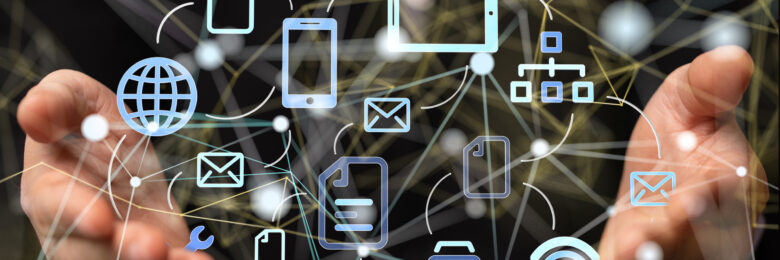
シェアリングエコノミーで活躍する企業を2つ紹介します。「Airbnb」「Uber」です。
どちらも有名な企業なので、知っている人は多いと思います。
シェアリングエコノミー事例紹介「Airbnb」の場合




Airbnbは、住宅をシェアするサービスです。自分の家やホテルの空き部屋を2000円〜4000円といった低価格でシェアするサービスになっており、物件によっては長期滞在も可能です。
貸す側を「ホスト」借りる側を「ゲスト」と呼び、それぞれにメリットがあるサービスになっています。
「ホスト」は、月単位で貸すよりも割高で貸す事ができます。
「ゲスト」は、1泊の料金を抑える事もでき、長期滞在もしやすいです。
心配なのは、セキュリティの問題ですが、シェアリングエコノミーの世界では「トラブルを起こすユーザー」は、ホストでもゲストでもこの世界に居づらくなります。
シェアリングエコノミーの世界では、信頼貯金がなければ貸す事も借りる事もできない社会だからです。
もし、泊まる度に、壁に穴を開けるユーザーが居たとして、そういう履歴が残っているゲストに部屋を貸すホストはいないでしょう。
逆に、毎回暴行事件を起こすようなホストの部屋に、泊まるゲストがいなくなるのと同じ理屈です。
これまで借りる側が圧倒的に強すぎた宿泊業で、フェアな風を感じるサービスです。
シェアリングエコノミー事例紹介「Uber」の場合




アプリを使って、配車するサービスです。
日本では、「UberEats」の方が有名で、タクシー業はあまり見かけないですが、世界では大きなシェアを確保しています。
こちらもセキュリティを心配している人がいるかも知れませんが、海外で普通のタクシーを呼ぶ方が怖いと思いませんか?
アプリを使って、評価の高いドライバーである事が分かっていた方が安全だと思います。
毎回ぼったくったり、強盗したりするドライバーを選ぶ人はいないでしょうし、毎回強盗を働く客を乗せるドライバーもいないと思います。
シェアリングエコノミーが普通になった世界では、「信用」がないと生きづらい世の中になります。
シェアリングエコノミーがもたらす未来


シェアリングエコノミーでは、これまで以上に「信用」が目に見える社会になります。
何かのサービスを利用する際、その人がどんな人なのかが相手に分かる社会です。
これまでの社会であれば、サービスを展開する側だけが一方的に情報を開示していました。なので、どんなお客さんか、実際に来るまで分かりません。この辺りがあまりにもフェアではなく、レンタル料の高騰を招いていたようにも感じます。
これは会社も同じで、面接の時は凄い実績をたくさん履歴書に書いていたのに、雇ってみたらほとんど未経験。そんな事は、割と多いと思います。
仕事の経験以外でも、普段から「SNSでどういった発信をしているか?」であったり、「どういったサービスを利用しているか?」も、一目瞭然となります。
1人1人の情報を精査すると時間が足りないのがこれまでの社会でしたが、そのあたりの課題は、オンライン化された仕組みであったり、AIが片付けてくれるようになります。
サービスを利用する側と、サービスする側が、お互いの信用を担保した状態で、資産をシェアする世界はすでに始まっています。
この動きは、ますます進んでいくでしょう。貸す側のAI化やロボット化が進み、シェアする負担が、限りなく0(ゼロ)に近づくからです。
- スキルはシェアする時代になっている。
- シェアリングエコノミーとは、空いている資産をシェアする仕組み。
- シェアリングエコノミーは、個々の信頼が可視化された世界。
ゲーム制作の新たな形:シェアリングエコノミーの活用法


シェアリングエコノミーが推進された世界では、ゲーム作りにも大変革が起こると思います。
なぜなら、ゲーム開発には多大なるコストがかかるからです。
しかし、秘密にしなければいけない部分が多すぎて、シェアの考えが浸透するまでには、まだ相当な時間がかかると思います。
どのゲーム会社も、開発中のゲームを公開する事ができないからです。人が足りないからといって、自由に人を引っ張ってこれない現実があります。
人を雇う場合は、信用のある開発会社や、コネクションを使う必要があります。
ただ、やっぱり時代は進んでいて、ゲーム作りの様子を公開しながら開発されている方がおられます。
僕もモバイルゲーム開発時代にかなりお世話になった岡本吉起先生です。
Youtubeで神ゲー作りを公開されていて、とてもすごい試みなのでみてみてください。
岡本吉起先生について:ストリートファイター2を開発されたゲーム業界のレジェンドです。そして、最近は「モンスト」も開発されたすごい方です。現在も、第一線で、さまざまなゲームを開発されています。
ゲームのアイデアも素晴らしいですが、チームビルディングも最高なのでみてみてください。
初心者でも参加しやすいプラットフォーム


スキルシェアリングが進むと、未経験者でもゲーム作りに参加しやすくなります。
自分の得意な分野だけで勝負できるからです。
ゲーム作りには、何か1つとびきり優れた武器を持っている方が良かったりするんですが、最近では大手のゲーム会社に入るのが大変だったりします。
ゲームクリエイターになりたい人は、とても多いので、非常に狭き門だからです。
ゲームの専門学校に入って、大きな賞を獲得したり、有名国立大学に入学していたり、高いレベルが求められています。
中には、入社試験を受ける前に諦めてしまう人もいるかも知れません。
ゲーム会社に入れなかった優れた技術や能力を持った人が、スキルシェアで得意分野の仕事を請けたり、あるいは仕事を買ったりする世界が来るように思います。
仕事を買うという発想は、少し未来すぎて理解されないかも知れませんが、確実にくる未来です。
シェアリングエコノミーでゲーム作りをする開発上の課題と解決策


ゲーム開発で、シェアリングエコノミーを導入するには、大きな問題があります。
それは、秘密にしなければいけない事が多いという事です。
開発現場は秘密だらけなので、一緒に開発した事のないメンバーを入れるのは、かなりリスキーになります。
大切なゲームのアイデアを盗まれたら大変という理屈はわかりやすいと思いますが、版権であったり、発売日であったり外に漏れたらいけない情報が山程あります。
版権とは、著作権の旧称ですが、アニメや漫画のキャラクターを使用する権利の事です。
ゲームのアイデアは、特許で守られていたりするので簡単に盗まれる事はありません。
むしろ、開発現場のちょっとした情報が漏れる方がやばかったりするので、社内のどの部署で何が開発されているかも秘密になっているケースもあります。
映画を極秘に作っていたとして、その公開に合わせてゲームを作っていた場合、使用しているキャラクターの情報が外に漏れたらやばかったりします。
よくわからない開発メンバーを入れて、表に漏れてしまったら大惨事なので、スキルシェアリングによって未経験の開発者が入り込むには、まだまだ辛い世界です。
しかし、この状況が、開発費を高騰させているように思います。一部の信用できるクリエイターを雇うのに、非常に高いお金が必要になります。
ただ、高いコストを支払ってでも信頼できる優秀なクリエイターが欲しい気持ちは痛いほどわかります。
- ゲーム業界にシェアリングエコノミーは導入しづらい。
- シェアリングエコノミーがゲーム業界に導入されれば、ゲーム作りに参加しやすくなる。
- ゲーム開発は秘密が多く、シェアしづらい。
シェアリングエコノミーによる未来予測とまとめ


ゲーム開発にスキルシェアを導入するには、まだまだ課題は多いと思います。
ただ、確実にスキルをシェアする時代は訪れます。ブロックチェーンの技術を使えば、開発者の認証システムや評価・報酬の分配も自動でできるようになる(しかも、Discord等の無料ソフトで実現可能!)時代は、もうすでにやってきています。
一般に降りてくるまでは、もう少しだけ時間はかかるかもしれませんが、変化はあっという間なので、今のうちに触っておくのが良いでしょう。
あとは、シェアする時代になった時に、考えなければいけないことがあります。
そうなってから考えるのも良いですが、そうなる前に準備する事も忘れてはいけません。今のうちに考えておかなければいけないのは、「シェアできるもの」と「シェアする場所」だと思います。
なんでもかんでもシェアしていると、内部情報が外にダダ漏れで、発売日に似たようなゲームを出されてしまったりするからです。
何をシェアするのか考えなければいけませんし、どこにシェアするのかも考えなければいけません。
特にシェアする場所には注意が必要です。
1日や2日で簡単に作れるものではないからです。
僕がシェアする場所として今考えているのは、公式LINEです。今はまだ数えるだけしかお友達登録していただいている人がいません。
しかし、いずれ、ゲーム開発に必要なメンバーをこのコミュニティから獲得する時代が来ると考えています。
クリエイターは、シェアする場所を作る時代。僕はそう思います。
以上、さしあたり、今思う事でした。
ここまで読んでいただけてありがとうございます。
皆様の良い人生の一助になれば。
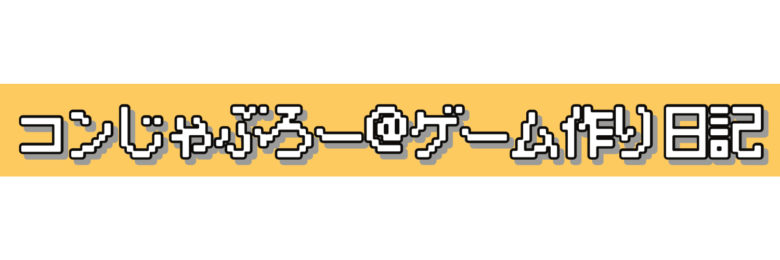








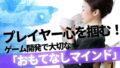

コメント