世の中、難しいことが多すぎて気持ちが萎える…。
気づいたら、その壁の大きさに不平不満をこぼしてしまう…。
周りの人が極端に楽をして見える…、そういう方はこちらの記事をどうぞ!
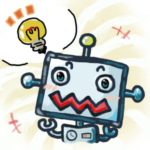
こんにちは!コンじゃぶろーです!
ゲーム開発は非常に難しい道のりです。その技術は多岐に渡り、尚且つ広く浅い教養と、長期的に持続可能な気力が必要になるからです。ゲームを遊ぶのが好きだからといって、必ずしも開発に向いているとは言えない点も難しいでしょう。
私は、逆にゲームはあまり上手くありませんでした。それでもゲームクリエイターとして長く活動を続けてこれているのは、楽観的に壁にぶつかって成長してこれたからかなと思います。
「ピースオブケーキ!(ケーキ1ピースくらいなら簡単に食べれるね!(訳:これ簡単だね!))」
何か難しいことがあったとしても、まずはこの魔法の言葉「これ簡単だね!」を口に出すことで、全て乗り越えられそうな気分になれます。これがとても大事です。
もし、壁にぶつかった時に「うわぁ最悪だ…」みたいなことを言ってしまうと、それを聞いていた脳は、それを現実にしようとしてしまいます。言霊というか、ほとんど呪いの言葉に近いかもしれません。
すぐに悪態をついて自分に呪いをかけるぐらいなら、「これ簡単だね!」とポジティブな呪いをかけてあげた方が良いですよね!この記事を読んで、手軽にできるポジティブ思考を試してみてください。
本日の記事、重要なポイント
- ゲーム開発は、大量の情報で頭が混乱しやすい。
- パニックになりそうな事は、シンプルに考える。
「これ簡単だ!」の一言が持つ力 ゲーム開発の困難な場面でポジティブ思考を活用する

ゲーム開発は、とてもややこしいです。
情報量が多いので、パニックになりやすいのですが、一人でゲームを作る時は、まだマシだったりします。規模も小さいので、データも把握できる量に収まりやすいです。
しかし、チームでゲームを作ろうとすると、規模も大きくなります。人が増えるほど、より複雑になりゲーム開発も難しくなります。
また、人が集まると「貢献度」という厄介なものも発生します。貢献度欲しさに「難しい仕事」を担当したとアピールする人が出てくるとどうでしょうか?皆が評価を求めて、少しずつ自分の仕事を複雑にしようとするだけで、ゲーム開発は困難さを極めます。
まず、ゲームは困難なものになりやすいという意識をチームで共有し、「これ簡単だね!」が口癖になるようなマインドを持つ必要があります。ここを見落とすと、長期間開発した末に、ゲームが完成しないという事にもなりかねません。
情報の混乱を避けるためのポジティブアプローチ


まず、ゲームは情報が非常に多いです。
画像データにサウンドデータ、シナリオデータに各種パラメータ。さまざまなデータを処理するプログラム。その全てを、確認するだけで1日がかりだったりもします。
さらに、プログラムのコードは、ぱっと見で理解しづらいので、アウトプットされたゲーム画面を実際に見ながら確認しなければいけない部分もあるでしょう。1つのエンディングを確認するのに最低8時間かかる規模のゲームであれば、その全てのデータに目を通すだけで1〜2週間かかることもあります。
過去、現在、未来の情報が交錯するゲーム開発


ゲームは5次元でできています。
今、僕たちが暮らしているのは4次元だと言われています。
0次元が点の世界。1次元は、点が集まった線だけの世界。2次元は、線が集まった平面の世界。3次元は、平面が集まった立体の世界。そして4次元は立体が集まり、時間軸のある世界です。
5次元は、今僕たちが暮らしている世界が集まった世界と言われています。
過去、現在、未来が同時に存在する世界だったり、パラレルワールドと呼ばれる同じ空間がたくさんある世界と言われています。4次元世界にいる僕たちには理解が難しいです。しかし、ゲームのデータを全て同時に見れる世界をイメージしてもらえれば理解しやすいかもしれません。
僕らの世界ではあり得ないですが、ゲームの世界ではパラレルワールドのように、同じ世界がいくつも存在します。ドラゴンクエストは、世界で累計8400万本売れています。という事は、ドラゴンクエストの世界が8400万個あるという事です。
ゲームは、次元が1つ違う。だから、そんなものを作るのに、混乱しないわけがないんです。
全ての選択肢が同居するゲームの世界


ゲームの中には、始まりから終わりまでが収録されています。
そして、全ての選択肢と、その答えが同時に存在します。量子力学の世界のようですね(正解と不正解が混在している世界)。量子力学ってなんだ?と説明を求められても、解説を聞いてもよくわからないですよね。
ゲームの構造は、それくらい複雑になりやすいものだという事です。
シナリオを考える時に、1つの分岐を用意すると、それ以降のシナリオを2つ用意しなければいけなくなります。当然、分岐が3つあれば3つです。
つまりは、ゲームならではの「IF要素(プレイヤーの選択によってエンディングが変わる)」を入れると、シナリオ量は倍々ゲームで増えていきます。
小説のように1方通行のシナリオを書くだけでも大変なのに、用意した分岐の数用意しなければいけない世界。想像しただけでゾッとしませんか?
- ゲームは5次元?過去、現在、未来の情報が混在している。
- ゲームには、始まりから終わりまでの、全ての選択肢が同居している。
シンプル思考でパニックを避ける
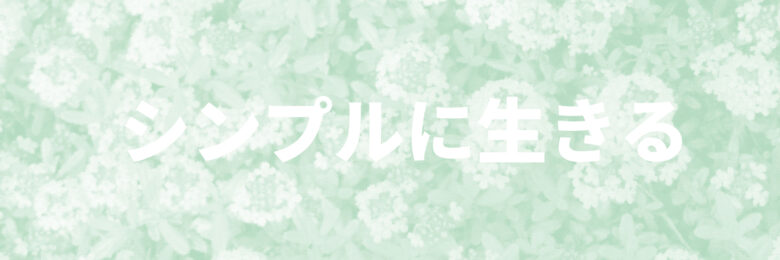
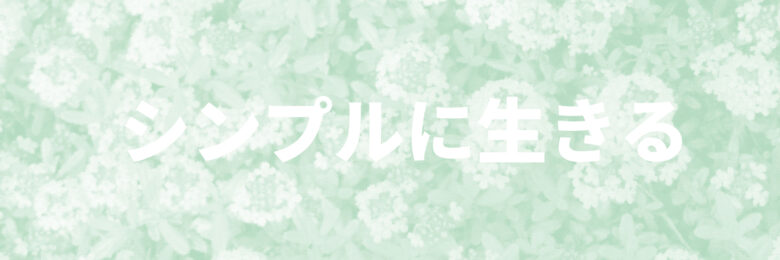
ゲームは、普通に作っているだけでパニックになります。
しかし、だからこそ価値が生まれます。プレイした人によって、内容が変わるのはゲームの醍醐味です。毎回プレイして同じであるなら、アニメや小説、漫画の方が良いでしょう。ゲームである意味という点を突き詰めると、「選択肢」と「マルチエンディング」は重要な要素と言えます。
結果がたくさんあれば、ワクワクする気持ちも生まれるからです。
ただ、その面白いものを作る為に、クリエイターがパニックになると、最悪完成しないという事も起きてしまうので、混乱しづらいチームを作らなければいけません。
「これ簡単だ!」と声に出してみる


まず、「これは簡単だ!」と声に出して言って下さい。
それこそ、チームメンバーに聞こえるような声がいいです。シンプルに考えられる人の方が優秀である。そういうルールを浸透させる必要があります。
複雑な処理を対応した人が偉い。そういうルールだと、自分の不幸自慢ではないですが、担当箇所の複雑さアピールが始まってしまうからです。
これまでに僕が出会ってきたリーダーや開発者で、成果が出ている人の共通点として「物事をシンプルにする」というのがあります。
先入観を排除して問題に取り組む


仕事ができない人ほど、不安がって物事を複雑にしていきます。単純に楽観的になれという事ではなくて、知恵を絞ってシンプルにする事が大切です。
トラブルが発生する案件は、全員で「複雑自慢(不幸自慢)」が発生するようなチームです。一見楽しそうに話していますが、出来上がる仕組みの全てが、複雑になっていきます。
良いデザイナーは、情報を処理するのが上手い。そういう意見を聞いたことはないでしょうか。
伝えたい情報を全部描くデザイナーは、情報の取捨選択ができていないので、雑念が混ざりすぎて相手の心にメッセージが届きません。伝えたい情報を整理して表現する事で、はじめてメッセージ性を高める事が可能です。ユーザーの心へ届けられるデザイナーは、非常にシンプルにまとめる事が可能です。
難しいと言う先入観があると、物事が複雑になります。
最初から難しいと言う先入観を排除するようにした方が良いです。
- まず、簡単だ!と声に出せば、少し肩の荷が降りる。
- 難しいという先入観を排除して考える
まとめ チームの合言葉:「これ、簡単だね!」


前向きで明るいチームというのは、開発していても楽しいですし、成果物も素晴らしいです。
何よりも素早く開発ができる上に、重大なバグも発生しづらくなります。
ここで間違ってはいけないのは、単純に早ければ良いと言うわけではなくて、構造的にシンプルにすると言う事です。
構造がシンプルなので、バグの修正も早くなり、開発コストもおさえる事が可能です。
アメリカでは、「これ簡単だね!」という意味で、「ピース オブ ケーキ!(ケーキ1きれ)」と言うそうです。
ケーキを1きれ食べるくらい簡単な事だという意味です。
「ピース オブ ケーキ!」
軽い感じで言い合えるチームが作れたなら、最高かもしれませんね。
ゲームに限らず、困難にぶち当たったら使ってみてほしいと思います。
以上、さしあたり、今思う事でした。
ここまで読んでいただけてありがとうございます。
皆様の良い人生の一助になれば。
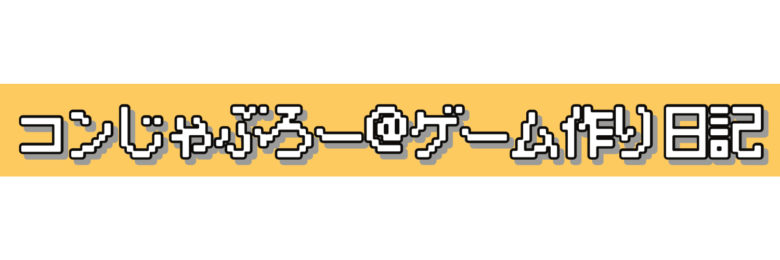


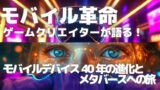






コメント