成績が悪いから進路が心配…。
もっと勉強すればよかった…。
学業で自信を失うと、立ち直るのが大変で辛いですよね。
ほとんどの人が大学を目指していた時代に、専門学校を選択して落ちこぼれ認定された僕が、就職氷河期で大卒が職にあぶれている時に、バリバリ仕事をゲットしてきた私が勉強法をまとめてみました。
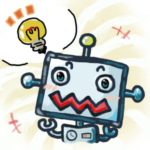
こんにちは!コンじゃぶろーです!
皆さん、こんにちは。今日は、学生時代の私が「おちこぼれ」と呼ばれた時期から、どのようにして逆転の成功を収めたか、その実録ストーリーをお届けします。勉強が得意でなかった私が、進路を決定する前に取り組んだ効果的な勉強法を紹介します。これは、成績に悩むすべての生徒さん、そして彼らを支える保護者や教育関係者の方々に捧げる、勇気と希望の物語です。
「勉強できない子の代表」コンじゃぶローの学校生活は、決して輝かしいものではありませんでした。授業での集中力の欠如、家庭での学習の非効率さ。しかし、そんな経験が後に私の大きな力となりました。おちこぼれのレッテルを貼られた私が、どのように学習の壁を乗り越え、自分の進路を切り開いたのか。この過程には、皆さんにも役立つヒントが隠されています。
この記事では、私が実践した「進路を決める前」の勉強方法を具体的に紹介します。忙しい学校生活、放課後の楽しい時間、そして夜の塾や習い事。そんな日々の中で私が見つけた学習の楽しさと効率的な方法。そして進路を決定した後、私がどのように勉強スタイルを変えたか。これらの経験が、あなたの学習方法に新しい視点をもたらし、勉強への新たなやる気を引き出すことでしょう。
最後には、勉強を楽しむためのマインドセットについても触れたいと思います。私の体験が、皆さんの学び方に新しい風を吹き込み、勉強に対する新たな情熱を呼び覚ますことを願っています。
この物語は、ただの勉強法の紹介にとどまりません。それは、どんな状況からでも自分の未来を切り開くための、勇気と希望のメッセージなのです。さあ、一緒に、おちこぼれからの逆転物語を紐解いていきましょう。
本日の記事、重要なポイント
- 勉強できない子代表『コンじゃぶろー』の勉強スタイル
- 教育環境・ルーティン
- 落ちこぼれ時代の気づき
- 「進路を決めた後」の勉強法
進路を見据えた勉強法:成績不振でも諦めない!
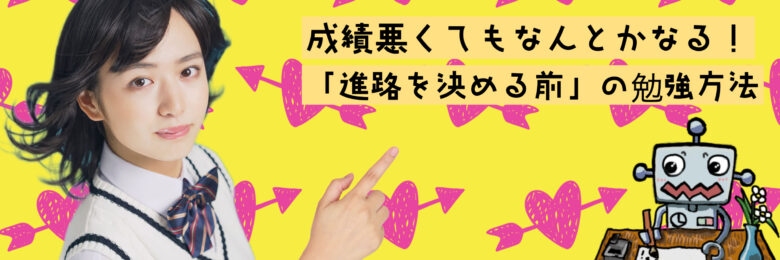
僕の勉強に対する姿勢を、思い出してみると、大きく変わったのは高校3年の夏だと思います。
「遊び」を仕事にすると決めた時です。
それまでの勉強で、重点を置いていたのは「興味のある事だけ勉強する」スタイルでした。
進路を決めてからは、「意味のある事だけ勉強する」スタイルに変わりました。
まずは、興味のある事だけ勉強していて、成績がすこぶる悪かった頃のお話です。
「勉強が苦手」からの脱却:コンじゃぶろーの学び方

僕の子供の頃の特徴は、「授業を聴かない」「家で勉強できない」の2点です。
これは、勉強できない子の代表的な特徴だと思います。
どういう感じだったのか詳しく説明します。
勉強が苦手な子の典型パターン①:授業を聞かない生徒
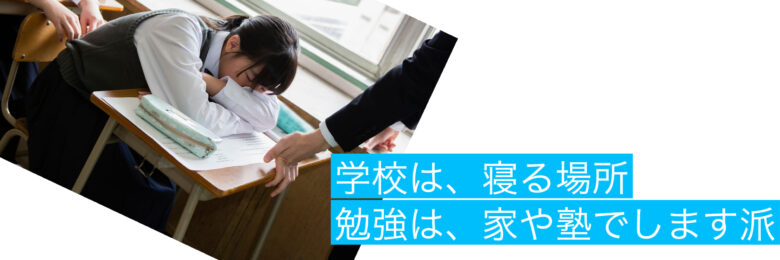
基本的に、授業は聴いていませんでした。
威張って言う事ではないと思いますが、その当時、レベルの高い進学塾に通っていて、学校の授業のレベルが低かったので、はっきりいってナメていました。
塾や習い事に通っているストレスもあったので、学校は「遊ぶ所」という意識が強く。先生の話は聴いていませんでした。
ただ、授業態度は真面目で、黒板をしっかり写していました。
今、思えば、これも先生の話を聴いていない原因の一つだったように思います。
進学塾には、通っていましたが、そこでも一生懸命黒板を写していたので、先生の話はあまり聞いていなかった気がします。
ただし、
学校でも、塾でも、楽しそうに教えている先生の授業は、楽しく聴いていました。
勉強が苦手な子の典型パターン②:家庭学習が進まない生徒

僕は、家でも勉強ができない子でした。
どう勉強できなかったかというと、↓こんな感じでした。
◇コンじゃぶろーの中間・期末試験前日のルーティン
21:00~ 勉強する前に部屋の掃除をはじめる
21:30~ 掃除が終わって椅子に座ったら、ちょっと休憩と「漫画」に手を伸ばす
22:30~ 漫画を読み終わったら、今日は徹夜するからと「夜食」を食べる
24:00~ 夜食食べながら見ていたテレビ(深夜番組)をズルズル見る
25:30~ ちょっと疲れたから仮眠をとる
5:00~ 明け方目が覚めて、焦って暗記する
これで、本人は大まじめに「勉強している」と思っていたから不思議です。
今だったら、勉強せずに、早く寝ていた方がいい点とれそうに思いますが、その頃の僕は「椅子に座っていれば」勉強してるという認識でOKとか思っていました。
1日のルーティンで変わる勉強成果

絵に描いたような「勉強できない」コンじゃぶろーですが、勉強をまったくしてなかったか?と言われると、そうではありません。
むしろ、人より「勉強」に時間を割いていました。
ただ、「勉強」に時間を割きすぎて、「頭がいっぱいいっぱい」になっていた為、「興味のある事」だけに集中していたように思います。
学校での学びと余暇のバランス

朝登校して、授業中は、楽しい部分だけ「授業に参加」していました。
「手を挙げて発言する」という事を、よくやっていたと思います。
進学塾で、先に勉強していたので、先生の話を聴かなくても分かっていたんですね。
先生にとっては、かなりムカつく存在だったように思います。
この当時は、「人前でアピールする」という楽しさを覚えた気がします。
根拠ない自信に繋がっていくので、失敗することも多かったですが、行動力にはなってます。
アクティブな放課後:遊びと学びの両立

部活が終わって解放されたら、友達の家に入り浸って遊んでいました。
主にテレビゲーム等で対戦して遊んでいたように思います。
学校は、楽しいコミュニティでしたし、夕方も友達と遊べてハッピーでした。
あんまり好きじゃなかった塾とか習い事に行く前の時間だったので、余計に楽しい時間でした。
夜の時間の使い方:塾や習い事での学び

17時頃に家に帰ってくると、そこから早めにご飯を食べて塾や習い事に行っていました。
小2頃から通っていたように思います。
- 進学塾:市内で有名な塾で、週5回通ってました。
- サッカー教室:大きな公園で、週1回通ってました。
- 書道教室:週1回通ってました。初段までいったと思います
ずっと毎日、何かの塾や習い事に通っていました。
それが普通で、特に忙しいとも思っていませんでした。
基本的に、予定が空いたら埋めるスタイル。
途中で書道教室が閉じた時も、マンツーマンの個別指導塾へ通うようにするなど、予定が何もない日はありませんでした。
高校に入って、塾のたぐいを一切やめて、全て「部活」に全振りした部分を含めて、いつも何かやってる状態だったので、社会に出てから「土日」返上で仕事するのも、そんなにつらくは無かったです。
ほとんど家にいなかったのも、社会に出てから変わってないポイントなので、僕の「基礎」は、この時できたように思います。
おちこぼれ時代から学んだ勉強のコツ

おちこぼれ時代の僕ですが、あれはあれで良かったなぁと思う事もあったので、その時の気づきをまとめてみます。
楽しいことから学ぶ:友達との時間がもたらす効果

友達と遊ぶ時間が、心の底から楽しめたのは良かったと思います。
その時に、遊んだ時の楽しさは、「ゲーム作り」に生かされているからです。
ほとんど、ゲームをして遊んでいたので、色んなゲームができました。
人がどういう時に楽しさを感じているのかを、ずっと体験していたので、ゲームを作る側に回った時に、彼らの楽しそうな顔が思い浮かぶようになりました。
彼らに届けているというつもりで作ったゲームは、とても売り上げが良かったです。
中途半端な学びから得た価値


学校も、塾も、習い事も、とにかく詰め込むスタイルだったので、全部覚える事はできませんでした。
覚える気もありませんでした。
ただ、広く浅く知識を覚える事ができたのは良かったです。
大人になったら、ネットで何でも調べる事ができるわけですから、全部覚える必要なんて無かったんです。
どういう公式があるか、おぼろげに覚えておけば、必要になった時に「確かあったはず・・・」という感覚で、何でも引っ張りだす事が出来るようになっていました。
幅広い知識が必要なゲーム開発には、とても有利な勉強法だったと思います。
休むことなき日常:「普通」の中に隠れた学び


ゲーム開発は、なかなかハードでした。
今の時代には、あまりないのかもしれませんが、僕が現役だった頃に土日の概念はありませんでした。
泊まり込みで仕事したりもへっちゃらだったのは、小さい頃から休みなく塾や習い事に通っていたからだと思います。
高い月謝を払って通わせてくれた両親に感謝です。
見られることで力を発揮する学びのスタイル


小さい頃の勉強法は、まさに「アピール」する為の勉強でした。
あまり実益の無い、勉強アピールです。
人によく思われたいと、ずーっと考え続けて生きてきたので、人前であれば勉強できるようになっていました。
もともと、人前だったら勉強できる性格なので、家で誰も見てない状況で勉強ができなかったのかもしれません。
進路決定後の学習スタイル大転換


高校3年生の夏、ゲーム業界へ行くと決めた僕は、勉強の方法ががらりと変わりました。
「時間主義」から「成果主義」に変化したのです。
このマインドチェンジによって、自分の本質を変えずに、成果の出る習慣を手に入れました。
あの日を境に「成果の無い事」をどんどん辞めていったのです。
黒板ノートはもう不要!新たな学び方へ
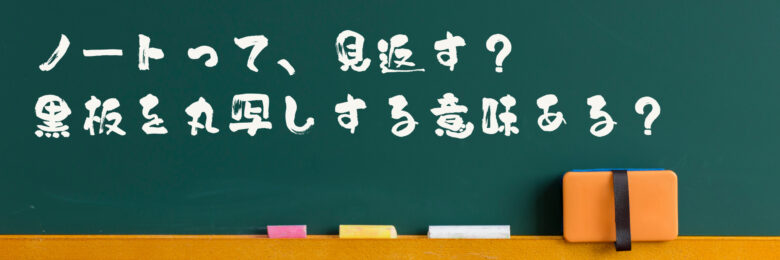
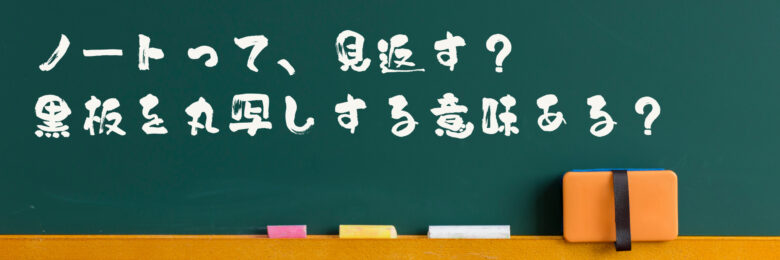
それまで、「勉強している感」しか出てなくて、後で一切見返さない作業を辞めました。
先生の話を聴く事に集中したのです。
ノートに写すのは、「大事だと思った事」と、「分からない事」だけになりました。
分からない事は自分で調べて、それでも分からなければ「質問」するようになり、より深くインプットできるようになりました。
家庭学習の見直し:新しい学び方の模索
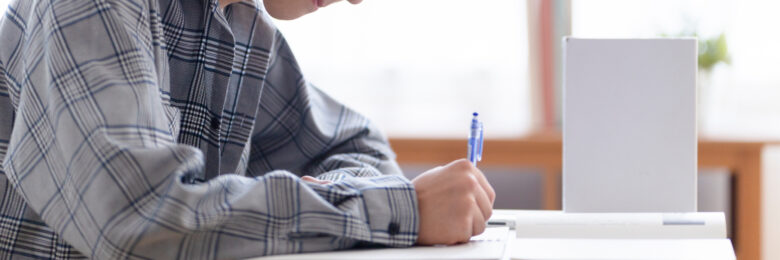
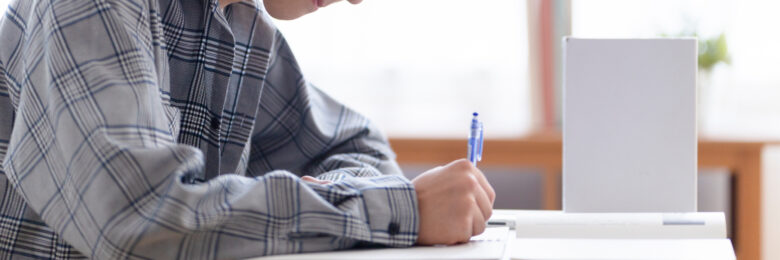
自分の部屋で、1人で勉強するのをやめました。
学校の課題は、学校の自習室でやるようになりました。
人間関係の勉強は、アルバイトでするようになりました。
とにかく人前に出なければ勉強できない性格だったので、どんどん人前に出るように努めました。
「時間主義」から「成果主義」へのシフト


子供の頃の僕は、完全に「時間主義」でした。
勉強に費やした「時間」で満足しているマインドだったように思います。
それを、「成果」だけを評価するようにしたら、ありとあらゆる事が変わってきました。
パソコンの操作方法も良く知らないITド素人が、国家資格である「基本情報処理技術者試験(2種)」まで取得し、なんとか学年の10本指くらいにはなれたと思います。
まとめ:勉強を楽しむためのマインドセット


「進路を決める前」と「進路を決めた後」で、大きく人生が変わりました。
しかし、最初から「進路を決めた後」のマインドで、学んでなくて良かったと思っています。
子供の頃の僕の根底にあったのは、「興味のある事だけ勉強する」でした。
もし、「成果」のみに着目していたら、今の原動力となっている「学ぶ楽しさ」が育まれていなかったように思います。
確かに、あの当時、勉強しているのに成績が悪かったのは、少し気になりました。
でも、「暗記」に重点を置いていた教育に疑問を持っていたので、特に大きな問題だと思っていませんでした。
成績が悪い自分へのイイワケとして、「暗記だけじゃダメ」という都合のよい答えを持っていたのかもしれませんが、結果的に良かったと思います。
成績悪くても平気でいる事ができました。
大切なのは、「その時、一番楽しむ事」だと思います。
もし、お子さんがおられる方は、参考にしてみてもらえるとありがたいです。
以上、さしあたり、今思う事でした。
ここまで読んでいただけてありがとうございます。
皆様の良い人生の一助になれば。
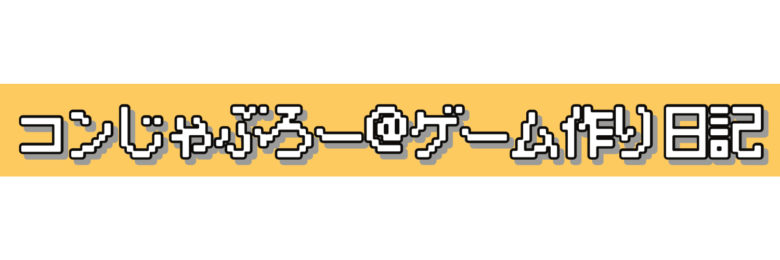











コメント