ゲームクリエイターになりたい!
何から始めたらいいかわからない!
そう言う強い思いを持っている人はこちらの記事をどうぞ。
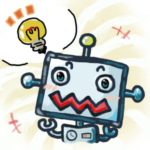
こんにちは!コンじゃぶろーです!
あなたが今遊んでいるそのゲームが、どのような道のりを経てこの世に生まれたか、考えたことはありますか?画面の向こう側で、創造と試行錯誤の連続、時には失敗と挫折を繰り返しながら、クリエイターたちは私たちが夢中になれる世界を創り上げています。その過程は、ただのゲーム作りというよりも、作り手自身の人生を豊かにする旅そのものです。
この記事では、ゲーム開発者としての道を歩むことの意味を、当事者になるための覚悟とともに深掘りします。ゲームをただ見るだけの人から、そのゲームを手に取り楽しむ人、さらにはゲームを創り出し、世に送り出す人へと変わる過程。それぞれのステージで作り手が直面する喜びと挑戦、そしてゲームがヒットする瞬間の背後にあるエッセンスに迫ります。
開発者と傍観者の違いは何か、そして実際に作り手として経験を積むことの価値は計り知れないものがあります。ゲーム開発者になるということは、ただ技術を学び、ゲームを生み出すということ以上に、自身の創造性、忍耐力、そして情熱を極限まで引き出すことを意味します。
どのような開発者になりたいのか、そのイメージを持つことの重要性から、ゲーム開発の各ステージでの心得、当事者になるために必要な覚悟まで、あなたがクリエイターとして一歩踏み出すためのヒントをこの記事で探っていきましょう。この記事があなたのゲーム開発の旅の、最初の一歩となることを願っています。
本日の記事、重要なポイント
- ゲーム作りの当事者
- 当事者と傍観者の違い
- 当事者は経験値が友里
クリエイターへの道: 必要な覚悟と成功への分かれ道

この記事は、僕のゲームクリエイターとしての成長をふり返りながら、どのように当事者意識が変わってきたのかを元に、当事者意識に関して解説したいと思います。
この記事を見て、「当事者」になる人が増えたらいいな!という想いで書いてみたいと思います。
ゲーム開発者の軌跡

ゲーム作りをしていると、段階的に当事者のレベルが上がるのを感じます。
おそらく、ゲームに限らず、どんな分野でも同じようにステージが上がっていく感覚があるんだろうと思います。うまく自分事にしながら見てみて下さい。
僕の場合は、大きく分けて6つの段階がありました。
①ゲームを見るだけ
②ゲームで遊ぶ
③ゲームを作る
④ゲームを販売する
⑤作ったゲームがヒットする
⑥ソーシャルゲームを作る
細かい段階を分ければ、もっと多くの段階があったように思います。
思い出せれば、それぞれ深掘りしたいと思いますが、今日はシンプルにまとめたいと思います。
ひとつずつ解説していきますね。
見学者からのスタート
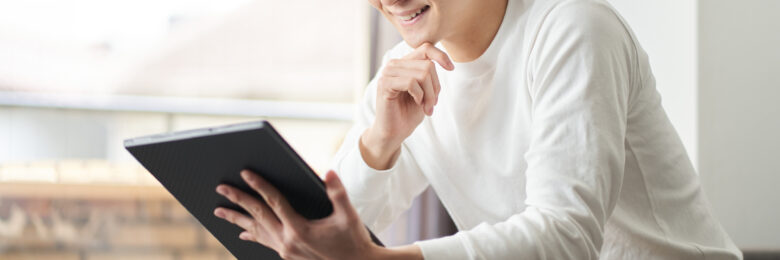
これは、ゲームを見ているだけの時期です。
「見る」という事に対して、当事者になった時です。
ちょうどファミコンが世に出た時でしょうか。
おもちゃ屋さんに、突如ファミコンが登場しました。
店頭にテレビが置かれて、大きなお兄ちゃん達がそこに群がっていました。
はじめて、スーパーマリオを目撃した時の衝撃はすさまじいモノがありました。
その当時、ラジコンが非常に欲しくてたまらなかったんです。
自分が操作した通りに、自由自在に動くマリオにワクワクが止まりませんでした。
ただ、3歳くらいだったので、列に並ぶ事もできずに見る事しかできませんでした。
ゲームを見た事がなかった僕が、ゲームを知っている当事者になって、おもちゃに対する印象ががらりと変わりました。
ゲームを楽しむ時期


はじめて、マリオで遊んだのは、近所の友達の家でした。
比較的裕福だった隣人の家では、マリオの他ゼルダ等店頭に並んでいたゲームがほぼ全部そろっていました。
僕は夢中になって遊びました。
見るだけだと分からなかった事は、ゲームの中のキャラクターが「コントローラー」を介して自分とつながる感覚でした。
見ていた時だと印象が薄かった音楽に驚きました。身体と一体化するような感覚になったのを今でも覚えています。
操作に合わせて、「効果音」が鳴る為、まるでゲームの世界の住人になったかのような感覚。
ゲームを遊ぶ人(当事者)になった事で、今まで使っていなかった脳の機能を使っているかのような感覚になりました。
実際、ゲームで遊んだ時、脳の空間認識力みたいなものが強化されるように思います。
初めてのゲーム制作


ゲームで遊ぶのが好きで、ゲームクリエイターになろうと思う少し前に、はじめてゲームを作る体験をしたのは、「RPGツクール」だったと思います。
確かパソコン用のソフトでした。
ゲームで遊ぶのが好きだったので、自分の遊びたい理想のゲームが作れるRPGツクールは、かなり魅力的なゲームでした。
「え!?RPGが作れるの?」と喜び勇んではじめてみると・・・。
ちょっと、ひきました。
かなりデータ量が膨大で意味が分かりませんでした。
サイコロの展開図の、もっとふくざつなやつ・・・。通じてますかね?
まず、フィールドの形。
RPGの世界では、街を歩いていて、家の中に入ると、当然家の中に入ります。
しかし、ゲームを作る側に立ってみると、印象が変わります。
ワープゾーンを用意して、別のマップへ瞬間移動させているので、家の中に入っているように見せているだけです。
RPGの街を作る時に、人を配置して何かをしゃべらせるだけで一苦労。
当然、セリフは全てうちこまなければいけません。
ショップ店員を作った時は、店員ではなくカウンターにセリフを入れて、プレイヤーがカウンターに話かけたら「セリフ」が表示されるようにします。
ショップ店員は、飾りでしかありません。
ゲームを作る当事者になって初めて気づくのは、ゲームの世界は作られているという事。
当たり前なんですけど、改めて、思い知らされました。
目の錯覚を利用した演出は、マジシャンのマジックのタネを見ているかのような感覚です。
ゲームを作るには、全ての部品を作る必要があるんです。
それ以降、ゲームを見る目が変わりました。どのゲームを見ても、どう作っているんだろう?という感覚になりました。無意識に設計図を頭に描くようなイメージです。
本格的なゲーム作りではなく、一般の人でもゲームが作れるというツールでこの難しさです。
ゲーム作る人は神なんだろうなと思いました。。
任天堂さんのゲームとか・・・見ただけで、そのボリュームがやばい事が分かります。
プログラマーの場合、マリオとかでも完コピしてみると、素材の量が見える化できるので、学びは多いと思います。
市場に挑む: ゲームの販売


ゲームの専門学校に入ってゲームをばりばり作り始めて、ゲームを作るという経験が徐々に積みあがっていた頃は、ゲーム作りになれてきて、その楽しさに夢中になっていました。
そろそろゲーム会社に入って、ゲームを販売する期に入るかな?と思ったら、そうスムーズにはいきませんで、ゲーム会社に入社しようとしましたが、ことごとく落ちてしまってしまって、その道がたたれそうになりました。
しかし、友人らで起業するという話があがっていて、そこに便乗させてもらう形でゲーム販売への道が開けました。
その時に、大きく変わったのは、「売れるゲームを作る」というスタンスです。
驚きですが、それまで「売れるゲームを作る」という意識がまったくありませんでした。
「面白いゲームを作る」という、とてもざっくりとした目標で作ってました。
今思えば、哲学や禅問答に近かったです(笑)。
そこから初めて、売れるゲームを作らなきゃと、思えるようになり、売れているゲームを徹底的に調べたり、研究するようになりました。
ヒット作の背景


いくつもゲームを作るようになって、欲しくなるのは自分のゲームをヒットさせたいという意識です。
ゲームを販売して、それに対するコメントが掲示板にのるだけで嬉しかったりしますが、欲はどんどん膨らんでいきます。
じきに、ヒットを飛ばしたいと思うようになりました。
のどから手が出る程欲しかったのと、その時に企画を教えてくれていた取引先の師匠からは、ゲーム企画者は、10年で何かヒットを飛ばせないと(代表作が無いと)やばいね、とも言われていたので正直ちょっと焦っていました。
3ヵ月に1本くらいのスパンで、次々作っていき、スマッシュヒットが飛ぶようになってくると、今度は自分の作ったゲームに勝てる気がしなくなってきました。
昨日の自分と戦っている感覚というか・・・。
あれほど欲しかったヒットなのに、ヒットさせないといけないというプレッシャーに変わりました。
毎日プレッシャーで吐きながら作り続けていました。
このころから、出す企画は100%採用されるようになり、無駄な企画書を書かなくなりました。
その空いた時間をゲーム作りに投入するようになりました。
ソーシャルゲーム開発の裏側
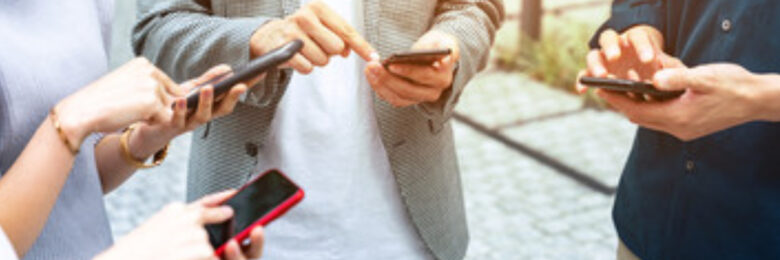
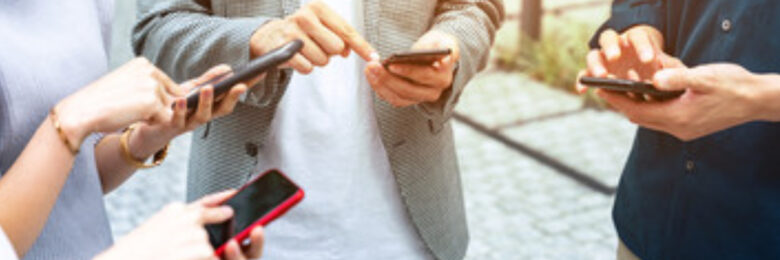
10年前の今頃は、ソーシャルゲーム全盛の時代です。
その当時の僕のメインフィールドは、ガラケーゲームでした。
それでも時代の流れは、スマホに移っていたので、スマホの勉強に必死になっていました。
スマホへの移行だけでいっぱいいっぱいで、ソーシャルゲームをフルコミットできていませんでした。
ちょうどそのころ、大手のゲーム会社が、スマホゲームの世界へなだれ込んでいた時期です。
元々、大手は、携帯ゲームへの参入に積極的ではありませんでした。
だからこそ、僕みたいな学生上がりのベンチャーでも戦えたわけですが・・・。
その頃は、ゲーム業界全体がかなり下火になっていて、それとは対照的にソーシャルゲーム界隈のゲームは恐ろしい売り上げを叩き出していたので、それに飛びつく形で、大手が参入してきました。
スマホの勉強だけではダメだと思ったので、ソーシャルゲームの勉強もこつこつはじめました。毎月課金額を決めて、課金しながら色んなゲームで遊びました。
休日にソーシャルゲームのセミナーに参加したり、ゲーム専用のサーバー構築の相談会に参加したりしていましたが、勉強する事がいっぱいで目から火花がでていたと思います。
そんなこんなで、僕もソーシャルゲームの世界に踏み込むわけですが、これは盛大に失敗してしまいます。
完成させる事ができなかったんです。
作ってみると分かる。
パズドラやモンストの凄さです。
その後、何度かソーシャルゲームを開発されている方とお話する機会がありましたが、ソーシャルゲームは、とにかくソーシャルゲーム自体を遊びつくす必要があります。
ソーシャルゲームは、そのウェイトのほとんどは「運営」にかかっています。
楽しいコミュニティ(楽しい世界)を構築する力が必要です。
応援される運営力が必須になるチカラなので、ソーシャルゲームをやった事が無いというのは勝負になりません。
ソーシャルゲーム内で、リーダーシップを発揮して、他のプレイヤーを巻き込んで1位を勝ち取るポテンシャルが無ければお金が稼げる運営はできない。
そう言い切っても過言ではないと思います。
- 当事者になれば、段階的に視野が広がっていく。
開発者と観客: 業界を見る二つの視点


僕のゲームとの向き合い方をふり返りながら、当事者になった時の視点の違いを解説してきましたが、当事者と傍観者の差ってなんなんでしょうか?
当事者と傍観者の違いは、注目されているプレッシャーだと思います。
セミナーやミュージカル等を想像してもらえると分かりやすいですが、客席から舞台を見るのと、舞台上から客席を見る場合とで、自分を見ている人の数が全然違うと思います。
今、注目されている。
そういうプレッシャーがあります。
視線を感じるというのもあると思いますが、今まで自分が見ていた対象に自分がなった時に、今まで自分が向けていた視線の強さを、人数分感じてしまうのだと思います。
実践から学ぶ: 当事者の経験値の重要性


当事者になると、獲得できる経験値が爆増します。
見られているというプレッシャーがあるので、緊張感をもった状態がインプットとアウトプットの質を激増させます。
今まで自分が傍観者として、どこまで見ていたかによるかもしれませんが、傍観者だと当事者の悪い部分がよく見えるんです。
出る杭はうたれるという言葉があるくらいなので、当事者は集中砲火をうけやすい立場です。
そういう状況で何かを生み出していくと、1人では出しきれないダメ出しが発生します。
その全てのダメ出しを受け止めていたら心を壊してしまいますが、数個でも受け止めて改善すればものすごい成長になります。
当事者になると、その機会が圧倒的に増えます。
目指すべきクリエイター像: 成功へのイメージ力


当事者になると、成長が凄いという説明をしてきました。
どんなことであっても、「こうなりたい!」と思わなければ何者にもなれません。
だからと言って、焦る必要もなくて、ぼやっとした目標と、それに向かって毎日楽しむということ
誰よりも楽しく成長し続けることができれば、自然と目標とするステージに立てるようになります。
くれぐれも目標を達成することだけに集中しないことに気をつけて進みましょう。
自ら行動し、楽しく得た知恵のみが、未来を照らすからです。
- 注目されているというプレッシャーが大切。
- 当事者になると、経験値が激増する。
まとめ: 当事者になるための決意


当事者になるという事について、まとめてみて、改めて感じるのは、当事者って覚悟がいるなぁという事です。
ゲームクリエイターになる!と覚悟できたから、順調に当事者のステップを登ってこれたような気がします。
高校生の頃は、できる事なら一番後ろにいたい恥ずかしがりな生徒でした。
恥ずかしがりやなのは、今も変わりませんが・・・。
当事者にならなければ、何もできないという事に、ずっと悩んでもいました。
晴れ舞台とか、恋愛にしてもそうですが、指をくわえていても何もできないんです。
何度も、悔しい想いをして、そういう想いが強かったからこそ、当事者になった時にパワーにもなったので、あれも必要な時期だったのかなぁ、なんて思えるようにもなれました。
以上、さしあたり、今思う事でした。
ここまで読んでいただけてありがとうございます。
皆様の良い人生の一助になれば。
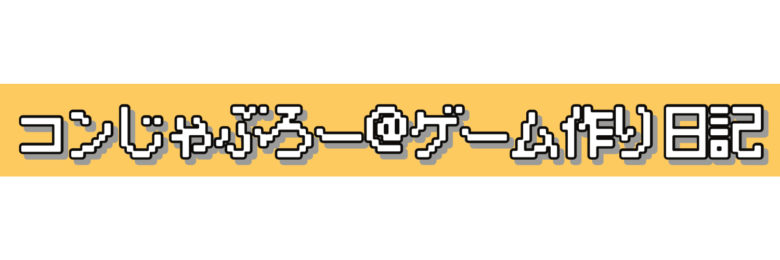










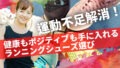

コメント