目の前のことばかりやっていたら、売り上げが下がってきた…。
どこかで新しい事を始めないと、技術力で置いてかれそう…。
クリエイターやエンジニアには、先を見据えた行動の選択が求められますよね。
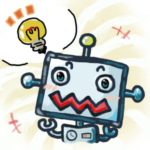
こんにちは!コンじゃぶろーです!
私たちの仕事環境は、常に変化しています。技術の進歩は止まることを知らず、それに伴い、業務手法もまた、日々進化しています。しかし、新しい技術を学び、取り入れることは、多くの場合、リスクを伴います。失敗の可能性、時間とリソースの消費、そして最も恐れるべきは、安定した現状を損なうことかもしれません。では、どうすれば、このリスクを最小限に抑えつつ、自身のスキルセットを拡大し、キャリアの成長を遂げることができるのでしょうか?
本記事では、「安定した仕事で新技術に挑戦する方法」をテーマに、リスクを恐れずに技術革新に取り組むための実践的なアプローチを紹介します。安定と成長を両立させるための戦略的な考え方と、具体的なステップを通じて、どのようにして変化の激しい現代の仕事環境に適応し、さらにはそれを利用して自身の価値を高めることができるのかを探ります。
新しい技術を学ぶことは、単に新しいツールや言語を覚えるということ以上の意味を持ちます。それは、新たな問題解決法を身につけ、未来の変化に柔軟に対応できる能力を養うことです。しかし、安定した職に就いている多くの人々は、日々の業務に追われ、新技術の習得に必要な時間やリソースを確保することが難しいと感じています。また、新しいことに挑戦すること自体が、既存の業務や成果に悪影響を及ぼすのではないかという不安もあります。
しかし、安定した環境であっても、技術の革新は避けて通れません。市場は常に変化し、新しい技術はその変化をリードする力となります。この変化の波を乗りこなし、自分自身を市場で常に価値のある存在とするためには、新しい技術への挑戦が不可欠です。
リスクを最小限に抑えつつ新技術に挑戦することは、個人の成長はもちろん、所属する組織や企業の競争力を高める上でも重要な意味を持ちます。安定した仕事の中で新しい技術に挑戦することで、リスク管理のスキルを高め、効率的な学習方法を見つけ出すことができます。そして、1つの新技術をマスターするごとに、自信と能力が増し、さらに多くの技術に挑戦する選択肢が広がります。
この記事を通じて、安定と成長を両立させるための具体的な方法を学び、自身のキャリアに新たな価値をもたらしましょう。変化を恐れず、リスクを管理しながら、新しい技術の習得に挑むことで、未来のあらゆる可能性に備えることができます。
本日の記事、重要なポイント
- 新しい仕事は、リスクが大きいから後回しにする
- 安定して予算を確保できる仕事を確保する
- 安定した仕事の中で、1つだけ新しい事を始める
安定した仕事での新技術挑戦の価値

事業をするなら、安定して予算を確保できるものが望ましいです。
予定した通りに入金されない可能性をゼロにしないといけないからです。少ない人数であれば、予算の確保も簡単ですが、大人数になるとなかなか厳しくなってきます。
なので、安定した仕事を受けるのが望ましいのですが、気をつけなければいけない事もあります。
今日は、僕の経験を元にベンチャー企業が序盤にとる方法の1つを共有します。
新技術への挑戦の重要性

会社を起業する場合でも、サラリーマンであっても、リスクの大きい仕事を受けるのはなかなか厳しいです。
会社の維持費によって変わりますが、取れるリスクを考えなければいけません。
僕がやっていた方法は、5%から10%新しい事(リスク)をとるという方法です。
学生あがりだったので、知識や技術が高かったわけではありません、もちろん経験があったわけでもないです。
狙って出した数値ではなくて、悲鳴を上げながら、落ち着いた数値です。
今日紹介する方法を試して、今の自分の状況に合わせてリスクを調整するのが良いと思います。
全くやった事のない仕事は、リスクが大きすぎる


全くやった事のない仕事は、リスクが大きいので取らないのは当然と思う人もいるかもしれません。
しかし、学生あがりのベンチャー企業にくる仕事って、新技術すぎて受け先がない仕事ばかりだったりします。
学生の寄せ集めだったので、とにかく取れる仕事はどんどんとっていく形になり、今思ってもリスクを多めにとっていたなぁと思います。
あれやこれやと、全力で走っているうちに、その当時、大阪では他に1社くらいしかやっていなかった技術の仕事をしていたりしました。
リスク回避しながらの技術革新


新しい技術っていうのは、誰に聞いても答えが返ってこないので時間がかかります。
使用する機材やソフトも海外のもので、問い合わせも英語になりますし、参考になる技術サイトや掲示板は、すべて英語になります。
手頃なサンプルもありません。
なので、時間もかかります。
たまたま、技術力のかなり高いメンバーがいたので運よく助かりましたが、あまり取るべき手段ではなかったと思います。
時間とリソースの管理


新しい技術を使って実現できない時、その技術を使わない方法を考えなくてはいけません。
さらに知らない技術をリサーチする。知らない技術を研究する。別の方法で作り直す。の3つを同時にこなさなければいけません。案件規模にもよりますが、人数も3倍になってしまいます。
正直、人数を3倍かけて対応できれば良いくらいの話ですが、それを他の業務をやっているメンバーを時間外に寄せ集めて対応する形になってしまいます。
これは、離職率も高くなりますし、かなりのリスクですよね。
- 会社組織は、取れるリスクを考えないといけない
- 新しい技術にはリスクが、伴う
- 新しい技術でミスすると、対応に3倍のコストがかかる
安定事業の重要性と予算の確保


安定して予算を確保できる事業があれば、それを優先すべきです。
誰か特定の人がいないと対応できない事業は、安定度が低いので、他の人ですべて対応できるような事業が望ましいです。
安定していない状態を「トラックナンバー」という言葉であらわしたりします。
メンバーが、トラックで轢かれたり突然いなくなった時に対応できる人数を表していて、トラックナンバー1だと、1人いなくなったら動かない状態で、トラックナンバー2だと、2人いなくなったら動かない状態になります。
数字が小さくなるほど、リスクが高い状態です。
安定して対応できる仕事は、「誰でもできる仕事」にしておく必要があります。
成功企業の安定事業の秘訣


事業がうまくいっている会社のほとんどは、ものすごく安定した事業を持っていたりします。
大手の会社は、世にあまり知られていない地味な事業を持っていて、それで予算を確保しているので、多少リスクをとった開発をしても問題なかったりします。
裏技とか、抜け道とかではなく、地味で利益も少なくて誰もやらないような事業を、極力手がかからないような仕組み作りをして売り上げを出しています。
店舗営業のほとんどを、アルバイトで対応できているマクドナルドは、その仕組みが神がかっています。
簡単にマネできないからこそ凄いんですけど、マニュアルや教育制度を整備しているからこそ、できる技だったりします。
予算確保の戦略と限界


極力リスクを取らないで進む方が安定はします。しかし、そこには落とし穴があります。
リスクを取らない安定した仕事(完成までのルートがイメージしやすいもの)は、増やせば増やす程事業を拡大しやすいです。
なので、人をどんどん増やしてしまいがちです。
人を増やして、やっていることが変わらない。この状況が落とし穴です。
何年も続けていると、必ず仕事がなくなってくるからです。時間が経つにつれて、他の会社もどんどん参入してきます。
新しい技術を持っている会社にどんどん奪われて、いつの間にか先細り。
気づけば、大量の人が社内で、仕事のない状況になってしまいます。
- 安定した予算を確保できる事業を優先する
- 安定した事業は、「誰でも対応可能」という状況にしなければいけない
- 新しい技術に手を出さなければ、いずれ仕事がなくなる
新技術にチャレンジする方法


仕事はどんどんとる。人も増やす。そうして、いつか先細りになって。大量に人が余る。
普通にやっていても、定期的に「技術力」が無いことを理由に仕事が受けれなくなります。
また、景気が悪くなると問答無用で仕事は無くなってしまいます。
肌感覚ですが5年周期で、不景気のタイミングはやってきているので、景気の良いタイミングこそ、時間を作って技術研究に打ち込まなくてはいけませんが、なかなか手に付きません。
苦しい時期を乗り越えた直後は、世の中に仕事が溢れてきますから、少しホッとします。
こういう場合、全体的にゆっくりしてしまいます。
本当に強い会社は、こういう時にこそ歯を食いしばって技術力を蓄えています。
1つの新技術に絞る理由


技術力の研究は、常に続けないといけません。
そうしないと、いずれ仕事がこなくなるからです。
ただ、リスクをたくさん取れないので、僕は5%から10%新しい技術に挑戦する方法をオススメします。大体1つ新しい技術に挑戦すると、ちょうど良いリスクをとることができます。
どうせやるなら、プロジェクト開始時に「今回は○○○に挑戦します!」と宣言して、全員で確認し合うくらいやったら、チームのモチベーションが上がると思います。
僕の場合は、駆け出しの頃に携帯ならではのネイティブ要素(GPSとかカメラとか)を使ったアプリばかり作っていたので、1つずつ習得する形になりました。
リスク管理と技術選択


ここで割とオススメなのは、これまで使っていた技術を別の技術に変更する方法です。
システムの一部分を新技術に置き換える事で、技術を研究します。
失敗しても、元の状態に戻すだけなので、比較的手が出しやすいリスクになります。
同じ作業ばかりしていると、コピペプログラムが横行して、技術力がどんどん下がっていく可能性もある為、積極的に違う方法を研究するのは悪くないと思います。
技術適用による選択肢の拡大
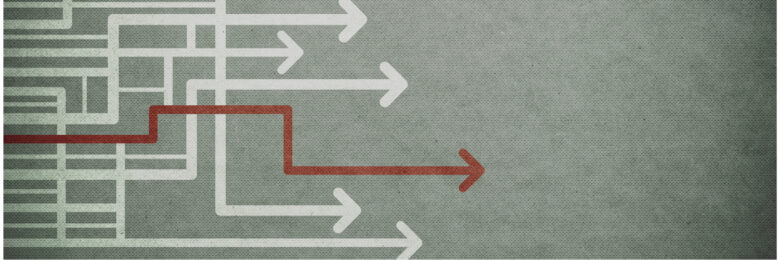
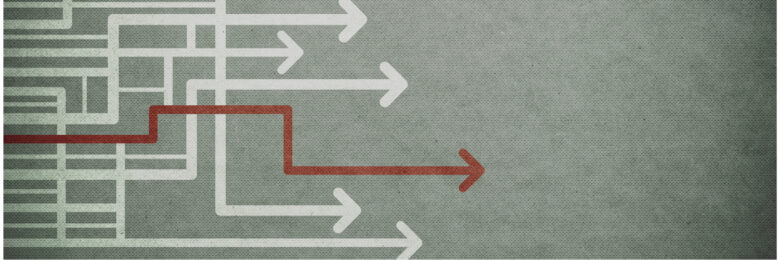
1つチャレンジした技術があれば、すぐに全体に共有するようにしましょう。
社内ライブラリに組み込む形で管理しておけば、自然に共有できますし、社内掲示板やチャットツールで共有するのが良いと思います。
1つであっても、10案件回せば10個の新しい技術が使用可能になります。
技術力が向上すると、作業効率も上がってきますので取れるリスクも増えてきます。こうして、少しずつ安定感が高まっていきます。
余裕が出てきたら、進む方向性も自由に選べるようになります。
ほんの少しのリスクでも、多人数で同時に実施していけば、あっという間に技術が蓄積される。これが会社組織が存在する大きなメリットだと思います。
個人では、なかなかこういう闘い方はできないですからね。
- 5%〜10%だけ、新しい技術に挑戦する
- 古い技術で対応可能なものを、新しい技術に置き換える
- 挑戦した技術は、全体に共有する
まとめ 継続的技術研究の価値と将来への影響


技術研究というリスクは、取らないといけません。
星の数ほど同じような会社があるこの時代に、現状維持は、衰退しているのと同じだからです。
休んでいる間に、他の会社が技術研究してあっというまに抜き去っていきます。
仕事がない会社は、技術研究せざるを得ないですからね。先頭を走っていても技術研究していないと抜き去られて仕事を失うことになります。
極論ですが、目指すべきは、社員が何もしなくても給料が支払えるくらい安定した状態だと思います。
余裕を持って、全員で技術研究や商品開発をしている状態が、僕の理想です。
夢物語かもしれませんが、僕はちょっとそこを狙っていたりしています。
IT技術が発達した時代だからこそ実現できる方法があるのではないでしょうか?
以上、さしあたり、今思う事でした。
ここまで読んでいただけてありがとうございます。
皆様の良い人生の一助になれば。
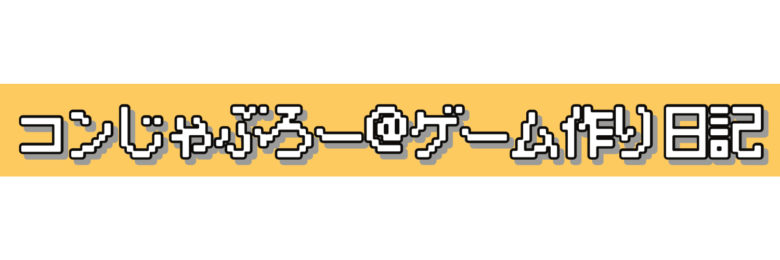













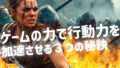
コメント