忙しい日常の中、ふと一息入れたいと思ったことはありませんか?
そういう方は、ガリヴァー旅行記を読んでみてください。
ファンタジーだけど、とても奥が深くて考えさせられますよ。
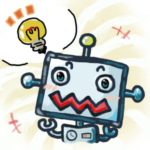
こんにちは!コンじゃぶろーです!
私たちは時代の大きなうねりの中で、日々を過ごしています。技術の進歩、社会の変化、そして私たちの価値観の変遷。この全てが交錯する中で、私たちは「新しい生き方」を模索し続けています。そんな現代において、ジョナサン・スウィフトの不朽の名作「ガリヴァー旅行記」が、予期せぬ示唆を与えてくれることをご存知でしょうか。
ガリヴァーの奇妙で魅力的な冒険は、ただのファンタジーではありません。それは、「風の時代」と呼ばれる今日この時に、私たちがどのように生きるべきか、どのような視点を持つべきか、そして未来への道しるべとなる重要な教訓を含んでいます。
この物語は、小人の国、巨人の国、空飛ぶ島、そして知的な馬が治める国と、様々な異文化との出会いを描いています。それぞれの国は、私たちの現実世界とは異なるルールや文化を持ち、ガリヴァーを通じて、私たち自身の世界観を問い直す契機を提供してくれます。
例えば、小人の国では、私たちが普段見過ごしている小さなことが、いかに大きな影響を持つかを教えてくれます。巨人の国では、力とは何か、優しさとは何かという根本的な問いを投げかけています。空飛ぶ島ラピュタでは、科学と技術の進歩がもたらす未来への思索を促します。そして、知的な話す馬の国では、倫理と知恵に関する深い洞察を与えてくれるのです。
本記事では、これらのファンタジーの世界を「風の時代」という現代の視点から読み解き、私たちが抱える日常の疑問や悩みに対して、新たな解釈と解答を探求します。ガリヴァー旅行記の各章を紐解きながら、私たちの「新しい生き方」のヒントを探っていきましょう。
さあ、ガリヴァーと一緒に、未知の世界への旅に出かけてみませんか?きっと、新しい発見と深い洞察が、あなたを待っています。
本日の記事、重要なポイント
- ガリバー旅行記 第一編 小人の王国
- ガリバー旅行記 第二編 巨人の王国
- ガリバー旅行記 第三編 空飛ぶ島から、東方の島々
- ガリバー旅行き 第四編 知的な喋る馬の王国
『風の時代』から学ぶガリヴァーの教訓
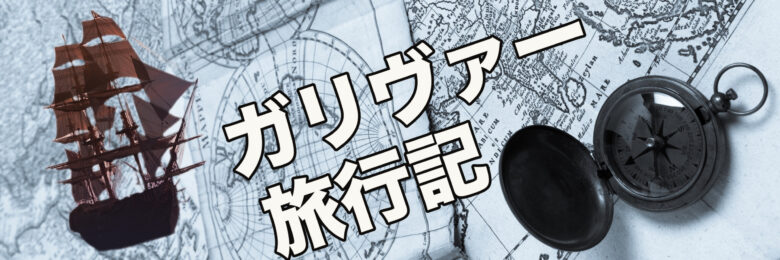
そもそもガリヴァー旅行記って、皆さんどれくらい覚えてますか?
遭難したガリヴァーが目を覚ますと、小人達にはりつけにされているシーンを思い浮かべる人は多いと思います。
ガリヴァー旅行記は、アイルランドの風刺作家ジョナサン・スウィフトによる長編小説です。
4編から構成されています。
- 小人の王国
- 巨人の王国
- 空飛ぶ科学の島「ラピュタ」、ラピュタに支配される国、魔法使いの国、不老不死の国
- 知的なしゃべる馬の王国
当時、流行していた旅行記の形式をとった物語で、最初の「小人の王国」の話が絵本や映画にされているので、それを知っている人は多いと思いますが、それ以降の編は、あまり知られていないと思います。
風刺作家が書いただけあって、その当時のイギリスや貴族、人間に対する風刺がすさまじかったりしましたが、子供から大人まで愛された素晴らしいファンタジーです。
社会や政治に対する「理想」と、それに対する「現実」を同居させたファンタジーで、人々が見ないようにして暮らしていた人間の愚かさを「第三者目線」で、気づかせる作品になっていた為、社会現象になり、爆発的に読まれました。
当時の政治家も勉強の為に読むくらい、政治学の入門書としても取り扱われています。
小人の王国と『風の時代』の教訓


「小人」と「自分」が、同居する世界。
最初は、ガリヴァーが遭難して、小人の王国に流れ着く所から始まります。
身長が10cm~15cm程度の小人達は、身長と同じように小さな不安を抱えて生きている。
作者的には、「小人」を、その時代の典型的なイギリス国民を風刺していたようです。
とるに足らない不安に悩まされて生きている姿が、その当時のイギリスの人々には気づきになったのかもしれません。
風の時代で読み解く「小人の王国」
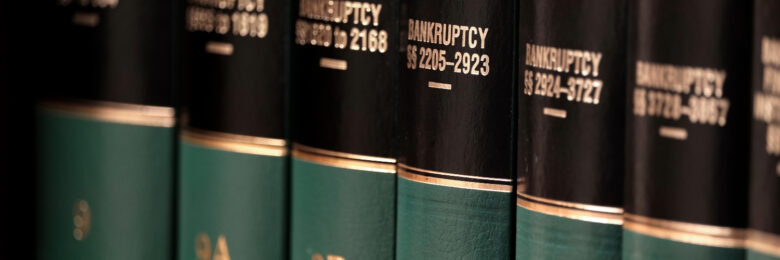
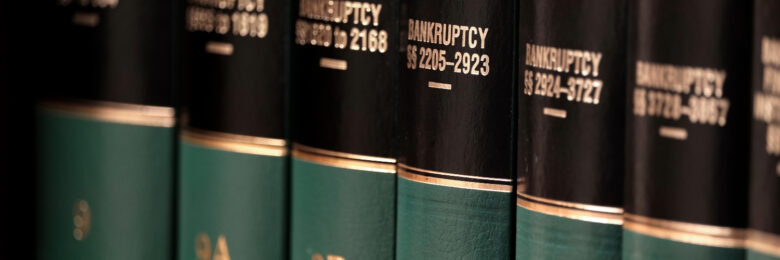
「小人の国」 を風の時代で読み解くと、 「巨大な力の使い方」です。
SNS全盛のこの時代では、突如大きな力を手にする事があったりします。
そんな時に、どのように立ち振る舞うのか?
力を手にしてからだと、焦ってまわりが見えなくなってしまうので、あらかじめ考えておくといいかもしれません。
巨人の王国と『風の時代』の視点


「巨人」と「自分」が、同居する世界。
小人の国の次は、巨人の国。この対比がまた面白いですね。
18メートルを超える巨人に捕まったあと、見世物小屋に連れていかれたり、宮廷の王妃のおもちゃとして扱われたりします。
巨人の王に質問される形で、当時のイギリスが抱える問題を取り上げるという、かなり斬新な切り口の風刺です。
風の時代で読み解く「巨人の王国」


「巨人の王国」 を風の時代で読み解くと、 「俯瞰してみるチカラ」です。
人間は、食物連鎖の頂点に存在していたりするので、気づきづらい視点を持つのが大切だと思います。
また、今後、格差が無い社会になると、より自分の上に立つ人間の事をイメージしづらくなるかもしれません。
環境や状況の変化が起きた時に、自分がしている行動を俯瞰してみる。
自分よりも、上位の文明があったとして、その上位の文明から自分を見たらどう見えるのか?
そういう視点を持つと良いかもしれません。
ガリヴァー旅行記:空中と東方の冒険


ヨーロッパの人々が、東方の国に抱く夢のような理想を題材にしています。
黄金の国ジパングとか、隣の芝に憧れる人が多かったかもしれません。
科学力・魔法・不老不死 等、夢のようなテーマに現実逃避する人々を風刺しているように思います。
次々と国を移り変わりながら、様々な国の人々を紹介するという形で、風刺していくスタイル。ちょっと「星の王子様」にも影響を与えているかもしれません。
ラピュタ:空飛ぶ化学の島と『風の時代』


「知識」と「無知」が、同居する世界。
「天空の城ラピュタ」のモチーフになった世界なので、知名度はめっちゃあるかもしれませんね。
島を飛ばすくらいの技術を持った科学者達の王国では、日々実用的ではない科学技術が研究されていて
作者が、科学者に対する嫌悪感みたいなものを感じます。
風の時代で読み解く「空飛ぶ化学の島 ラピュタ」


「空飛ぶ化学の島 ラピュタ」 を風の時代で読み解くと、 「目的意識」です。
情報や知識が、山のように手に入る時代になりました。
どんな情報や技術でも、Youtubeで検索すると出てきます。
作者が風刺している、学ぶ為の学びになっていないかチェックする感覚が無くてはいけません。
※「学ぶ」為に「学ぶ」とは、例えば、数学を学ぶ為に、どうしたら数学を学べるか考えるという事です。
目的無く暇つぶしの為の勉強になると、インプットの質が下がってしまいます。
目的を見失わないようにしたいですね。
バルニバービ:発明の国の教え


「発明」と「未完成(役に立たない)」が、同居する世界。
肥沃な大地を持つバルニバービの人々が、ラピュタの空飛ぶ島へ行って科学にかぶれてしまった結果、役に立たない発明ばかりに気をとられ、見当はずれな農業で大地を荒廃させています。
太陽の光をたっぷりあびたキュウリから、太陽の光を取り出す研究。
石をゴムのように加工して、枕を作る研究。
色々と、役にたたない研究が紹介されています。発明家に対する風刺でしょうか。
少し余談ですが、現代で少し役にたっている研究があったりします。
無学でも文章が書ける研究は、プリンターですし、屋根から作る建築技法は、ビルの建築で使われていたりします。
300年も前の作者は、凄いアイデアマンですね。
風の時代で読み解く「発明の国バルニバービ」


「発明の国バルニバービ」 を風の時代で読み解くと、 「誰の為の発明か意識する」です。
肥沃な大地を持っているのに、科学にかぶれて、役に立たない発明を繰り返す人々。
現代でも、特に求められていない発明は無いでしょうか?
趣味嗜好が多様化して、求められている物も大きく変化する時代です。
徹底的に、誰の為のサービスなのか?
誰が求めているモノなのかを考えなければいけません。
魔法使いの国:ファンタジーと現実の交錯


「過去」と「現在」が同居する世界。
魔法使いばかりがいる世界では、昔の偉人を降霊する事ができて、その当時の話を聴く事ができます。
作者は、昔の偉人を称える風潮や、過去の偉人の言葉に対して注釈をつけたり解説をしつづける人々への風刺を入れています。
その当時は、過去の哲学者の見解に関して、それぞれが好き勝手言う風潮がありました。
中には、建設的でないものもあったことでしょう。
過去にばかりとらわれている人々に対して、注意を促していたのかもしれません。
風の時代で読み解く「魔法使いの国」


「魔法使いの国」を風の時代で読み解くと、「真偽」を確かめるチカラです。
過去の歴史は、資料の量が少なく精度も低かった為にその真偽を確かめる術が無かったかもしれまん。
しかし、今は、インターネットがありSNSがあります。
嘘があれば、たちどころに露見する世界になりました。
しかし、本物であれば、爆発的に広まる世界になっています。
本物は、宣伝しなくても売れる。
偽物は本物にならざるを得ない。
ラグナグ王国:不老不死の謎と『風の時代』


「生」と「死」が、同居する世界。
不老不死が実現された世界の噂話をする、ラグナグ王国の人々。
ラグナグ王国に限らず、現代人も不老不死を願っている人が多いと思います。
300年前の人もそれを願っていた人が多かったんでしょうね。
作者は、そこにも風刺しています。
不老不死の国では、80歳になると社会的に死人と扱われ、それ以降は老いていく厄介者として扱われていて、死は、救済であるという説明をしています。
風の時代で読み解く「不老不死の国」


「不老不死の国」 を風の時代で読み解くと、 「健康寿命」です。
不老不死は、科学のチカラで現実味を帯びてきています。
ただ、年齢に限らずに、死んでいるのと変わらない状況というのは、常に突きつけられるようになりました。
長生きできても、寝たきりだったらつらいですよね。
健康な状態で長く生きるにはとか、若さとは何か?を意識して、心も身体も健康的に過ごす必要があると思います。
知的な話す馬の王国:『風の時代』で読み解く知恵と倫理


「知恵」と「野生」が同居する世界。
しゃべる馬の世界では、人間を模した猿っぽい生き物「ヤーフ」が紹介されています。
知的な馬の人々との対比で、邪悪で汚らしい毛深い生物として「ヤーフ」を紹介していますが、「人」の醜い部分を、客観的に描く事で、強烈な風刺になっています。
作者が、本当に伝えたかった事は、この章に詰まっているのではないでしょうか。
風の時代で読み解く「知的なしゃべる馬の王国」
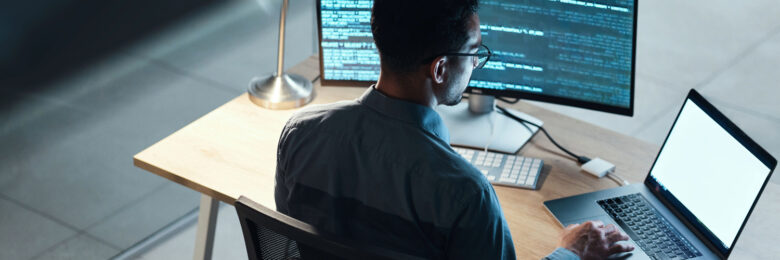
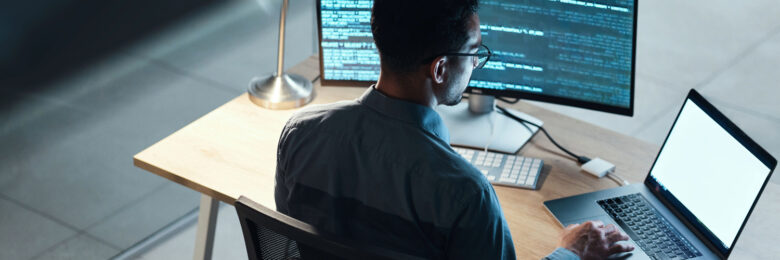
「知的なしゃべる馬の王国」 を風の時代で読み解くと、 「人間は邪悪で汚らわしい」と思う視点を持つ事です。
何でもかんでも邪悪だ!と思う必要はありません。
ただ、今まで正義として進めていた事業が、実は環境を破壊しているという事が、指摘されることもあります。
これも情報化社会になり、真偽が露見しやすいからでしょうか。
環境破壊に関する研究をしている教授が、「環境をよくする為には、何もしない事だ」と発言するくらいです。何かをすると、燃料として石油を使ってしまうので、CO2が増えていたり。
ソーラーパネルを設置する為に、石油を使って森林を伐採し、地盤が緩くなって土砂崩れになったりします。
本当に、必要なのは「邪悪な事をしているかもしれない」という視点を持つ事。
変化が激しい時代です。
正しいと思う事が、どんどん変化する時代です。
自分がやろうとしている事が、世の中に悪い影響を与えているかもしれない。
そういう視点を持った方がいいと思います。
ガリヴァー旅行記の総括:ファンタジーが映す現実世界
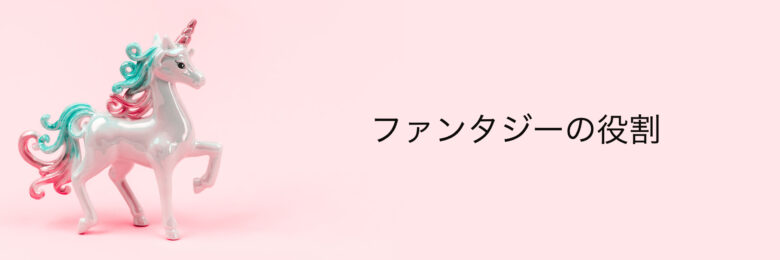
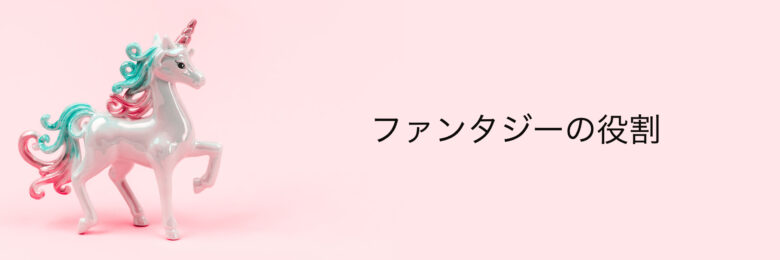
ファンタジーには、社会を風刺するという役割があるなぁと感じます。
実際の社会の出来事を描く場合、個人名や組織名を出すと問題になります。
しかし、ファンタジーの世界であると言えば、人は素直に耳を傾けます。
古代中国の王朝で、下手な事を言うとすぐに死刑になってしまったりする時代にも、「これは、とある古代の国の話ですが・・・」という語り口調で、王様へ諫言する(いさめる・忠告する)シーンが何度もあったりします。
かなり古代から、気づかいが必要だったんですね。
今は、変化の時代だ!と、ずっと言ってきましたが、変化は昔から山ほどあったと思います。
その都度、様々な犠牲があって一部が歴史や小説に記されてきました。
一部しか残っていないから、変化が無かったように感じているだけではないでしょうか。
過去の作品から学ぶことは大いにあると思います。
ファンタジーの中から、真実の一部が見えたりしませんか?
以上、さしあたり、今思う事でした。
ここまで読んでいただけてありがとうございます。
皆様の良い人生の一助になれば。
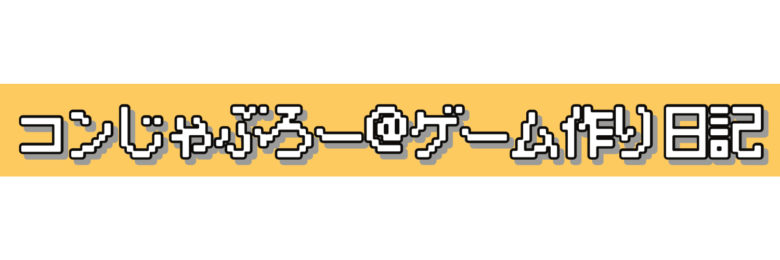
















コメント